魚を買うとき、切り身と丸ごと、どちらが本当にお得なのか迷ったことはありませんか?
スーパーで特売の丸ごとの魚を見つけても、「さばくのが大変そう…」「本当にお得なの?」と不安になり、つい扱いやすい切り身を選んでしまうこともあります。
しかし、切り身と丸ごとのどちらがコスパが良いかは、単に価格だけでは判断できません。
例えば、切り身はそのまま調理できる手軽さが魅力ですが、1枚当たりの単価は高め。
一方、丸ごとの魚は一見安く見えますが、さばく手間や食べられる部分の割合を考えると、必ずしもお得とは限りません。
また、冷凍保存のしやすさや、骨やアラの活用方法によっても違いが出てきます。
今回は、魚の切り身と丸ごと、それぞれのメリット・デメリットを詳しく解説し、どのようなシーンでどちらを選ぶのがベストかを紹介します。
家庭での使いやすさ、調理のしやすさ、コスパの良さを総合的に考え、あなたにとって最適な選び方を見つけましょう。
魚を無駄なく活用して、食費を上手に節約するコツもあわせてお伝えします。
コスパで選ぶ!切り身と丸ごと魚の賢い買い方
1.価格と食べられる部分の割合を比較する
魚を購入するとき、切り身と丸ごとのどちらがコスパが良いのかを判断するには、価格だけでなく、食べられる部分の割合を考えることが重要です。
丸ごとの魚は一見安く感じますが、内臓や骨、頭などの重量も含まれているため、実際に可食部だけの価格を比較すると切り身の方が合理的なこともあります。
例えば、サバを1尾500gで600円で購入した場合、100gあたりの価格は120円ですが、可食部は約60%とされているため、実際に食べられる部分の価格は100gあたり200円になります。
一方で、サバの切り身が100gあたり250円で販売されていた場合、すべて可食部として使えるため、丸ごと買った場合とのコスパの差はあまり大きくありません。
また、タイのような魚は丸ごと買うと可食部が50%程度になります。
例えば、1尾1.2kgで2,400円の場合、実際に食べられる部分の価格は100gあたり400円程度になります。
一方、タイの切り身が100gあたり450円で売られていた場合、可食部だけで計算するとほとんど差がないため、下処理の手間を考えると切り身の方が便利なこともあります。
ただし、アジやイワシのような小型の魚は、可食部の割合が高いため、丸ごと買ったほうがコスパが良いことが多いです。
例えば、アジ1尾200gが150円で売られていた場合、可食部は約70%とされるため、100gあたり214円程度になります。
一方、アジの切り身が100gあたり300円で売られている場合、丸ごと購入する方が経済的です。
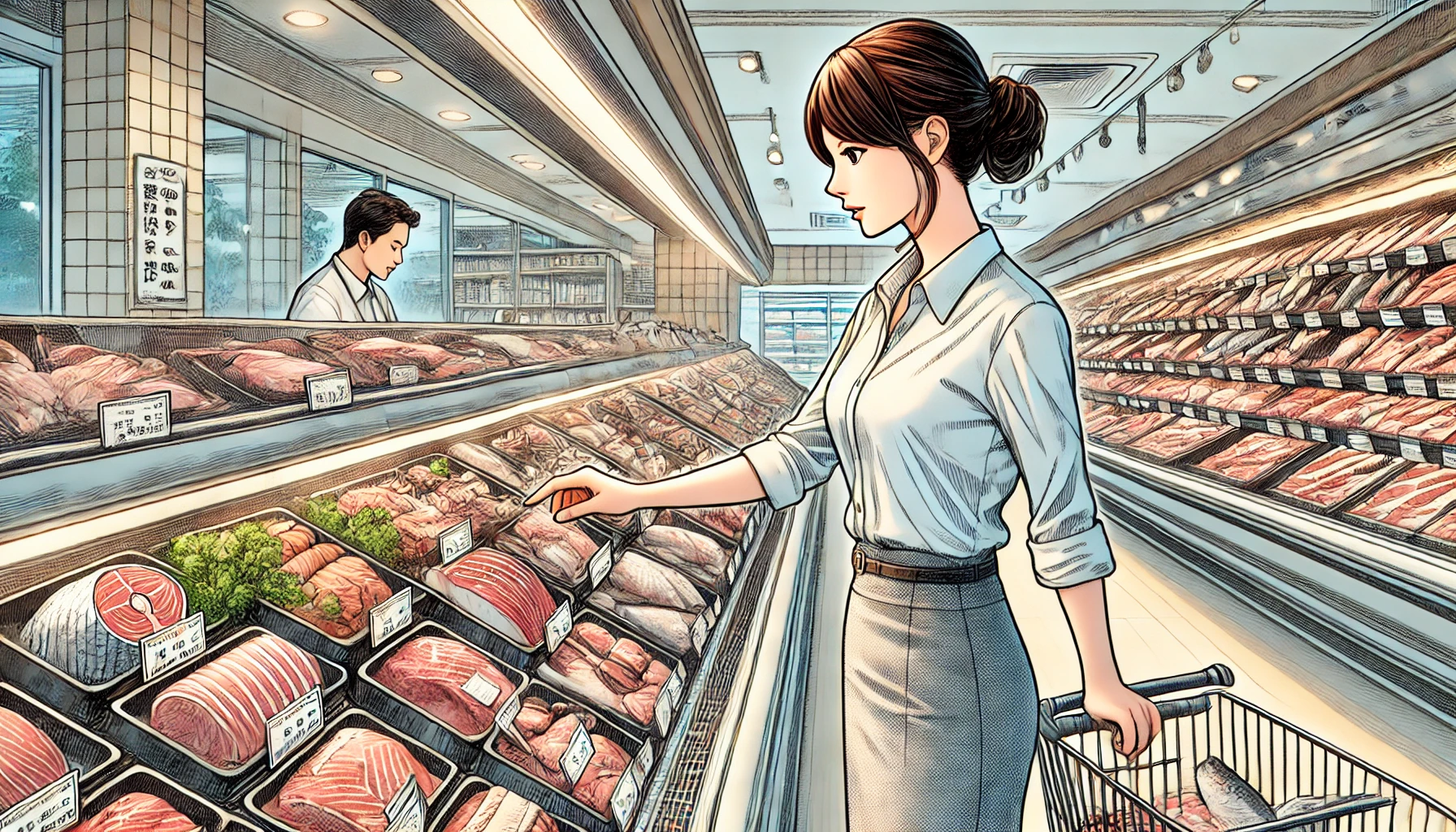
2.丸ごとはアラまで活用する
魚を丸ごと購入することで、切り身では得られない「アラ」を活用でき、食材を無駄なく使うことができます。
魚のアラには、身にはない旨味が詰まっており、上手に活用すれば、コスパを高めるだけでなく、料理の幅も広がります。
切り身は調理がしやすいですが、丸ごと買えばアラまで使えるため、よりお得に魚を楽しめます。
例えば、タイを一匹買った場合、身の部分は刺身や焼き魚にし、アラは「タイのあら汁」にするのがおすすめです。
タイのアラから出る濃厚な出汁は、味噌汁や塩汁にすると絶品になります。
アラから取れるコラーゲンもたっぷり含まれており、体にも良い一品になります。
ブリを一匹購入した場合、切り身は照り焼きや刺身にし、アラの部分は「ブリ大根」に活用できます。
骨やカマには脂がのっており、大根と一緒に煮ることで、深い旨味が引き出されます。
煮物にすることで、余すことなく魚の美味しさを味わうことができます。
また、アジやサバなどの小型魚は、骨や頭まで使って「骨せんべい」にすることもできます。
中温の油でじっくり揚げると、パリパリとした食感になり、おやつやおつまみにぴったりです。
カルシウムをしっかり摂取できるため、子どもにもおすすめのメニューです。
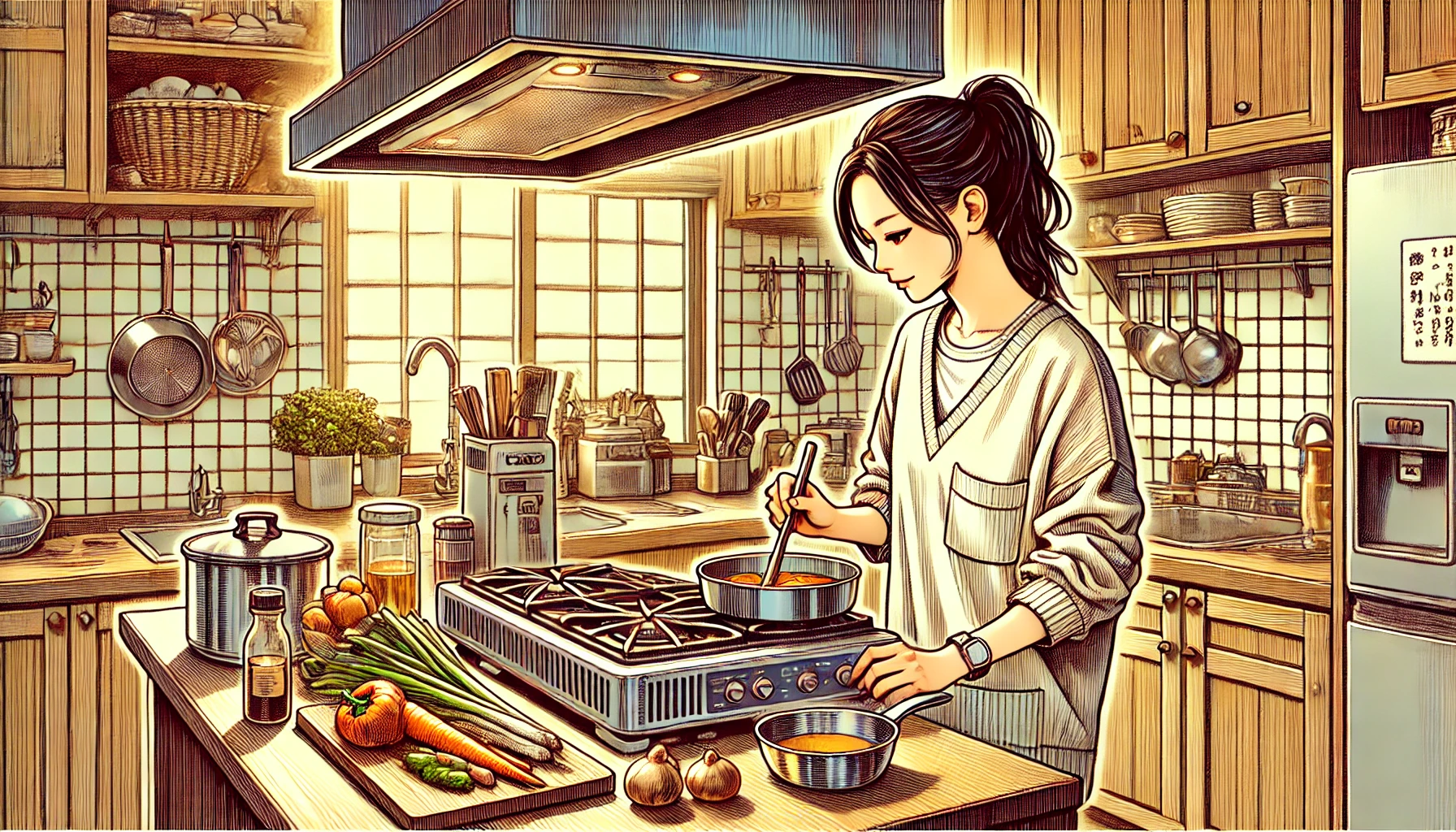
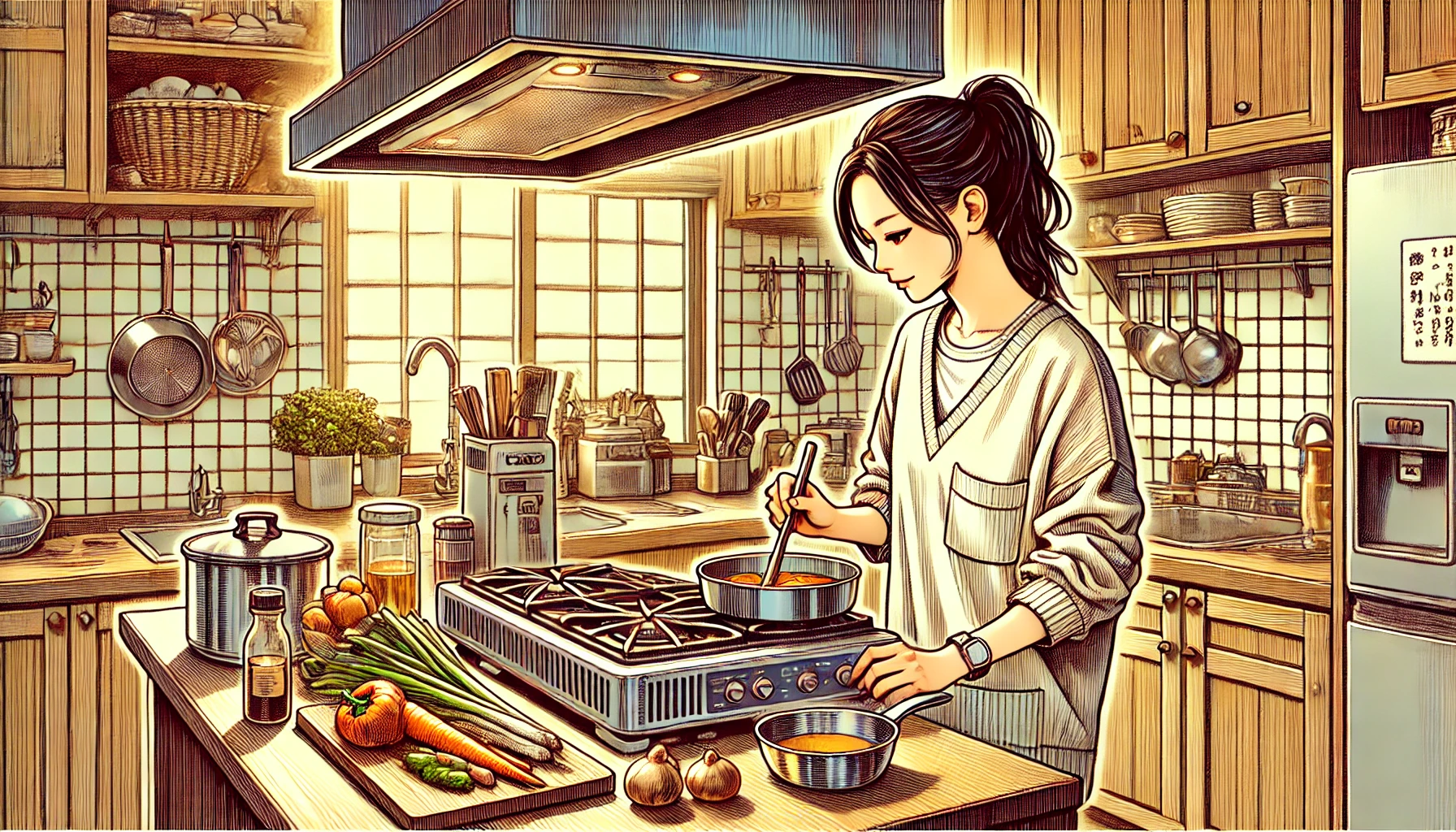
3.調理の手間と時間を考慮する
魚を購入する際、コスパを考えると丸ごと買うほうが安く感じることがあります。
しかし、調理の手間と時間を考えると、必ずしも丸ごとが最適とは限りません。
特に忙しい家庭では、下処理の負担を減らすことで、結果的に切り身の方が使いやすく、時間的なコスパが良くなることもあります。
例えば、タイを丸ごと購入すると、ウロコ取りや内臓の処理、三枚おろしの作業が必要です。
家庭で行う場合、これだけで10〜15分かかることがあり、さらに調理時間も長くなります。
一方、タイの切り身ならそのまま焼いたり煮たりできるため、手間なく調理できます。
忙しい日には、切り身の方が時短になり、結果的に負担が少なくなります。
また、サバを一尾購入すると、頭を落とし、内臓を取って三枚おろしにする必要があります。
家庭で処理する場合、シンクやまな板が汚れ、後片付けにも手間がかかります。
一方、サバの切り身を買えば、味噌煮や塩焼きにするだけで手軽に調理が完了します。
家事の負担を減らすという観点では、切り身を選ぶのも賢い方法です。
逆に、アジやイワシのような小型魚は、下処理が比較的簡単なため、丸ごと買っても負担が少なくなります。
例えば、アジは手開きにすれば10分以内に唐揚げやフライの準備ができます。
イワシは煮付けやつみれにする際に骨ごと使えるため、調理時間も短縮できます。
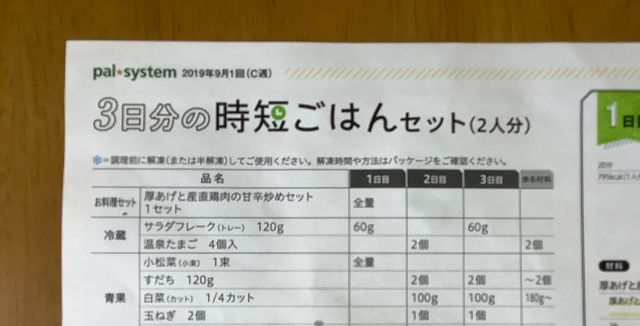
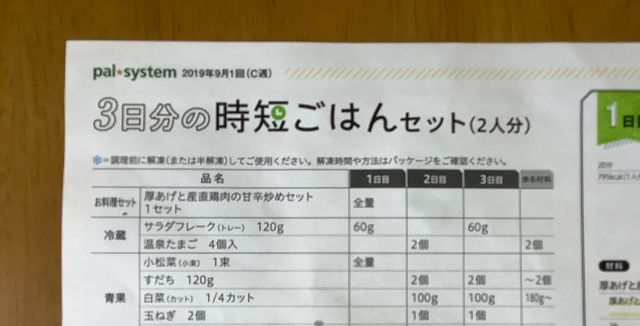
4.購入する量で選ぶ
魚を購入するとき、コスパを考えると丸ごと買うほうが安く感じることがありますが、購入する量に合わせて選ぶことも大切です。
家族の人数や食べきれる量を考慮することで、無駄なく経済的に魚を活用できます。
例えば、タイのような大きな魚は、1尾で1.2kgほどあり、丸ごと購入すると食べきるのに時間がかかります。
刺身や焼き魚、煮付けなどに使えますが、余った分を保存する手間も必要になります。
一方、切り身で買えば必要な分だけ購入でき、無駄が出ません。
特に、少人数の家庭では、切り身を選ぶことで使いやすくなります。
一方、アジやイワシのような小型魚は、丸ごと買うほうがコスパが良くなることが多いです。
例えば、アジを3〜4尾セットで購入すると1尾あたりの価格が下がり、唐揚げや南蛮漬けなどの料理に使えます。
小型魚は傷みやすいですが、すぐに調理すれば余すことなく使えて経済的です。
また、ブリやサーモンのような大型魚は、ブロックや柵で購入すると切り身より安くなることがあります。
例えば、ブリの切り身が100gあたり250円で売られていても、ブロックで買うと100gあたり200円程度になることがあり、必要な分だけカットして刺身や照り焼きにできるため、コスパが良くなります。


5.用途に応じて選ぶ
魚を購入する際、コスパを考えると丸ごと買うほうが安く感じることがありますが、用途に応じて適切な形を選ぶことも重要です。
調理方法や料理の種類によって、切り身と丸ごとでは使い勝手が大きく変わります。
例えば、すぐに料理を作りたい場合は、切り身を選ぶのが適しています。
サバの味噌煮や鮭のムニエルなど、すでに下処理が済んでいるため、そのまま調理できます。
忙しい共働き家庭では、時短になるため、結果的にコスパが良くなります。
一方、丸ごと購入すると下処理が必要になり、調理時間が長くなることがあります。
刺身やカルパッチョなどの生食用には、ブロックや柵で購入するのが向いています。
例えば、ブリの切り身が100gあたり250円で売られている場合でも、ブロックで買うと100gあたり200円程度になることがあります。
自宅で必要な分だけ切ることで、コスパが良くなり、余った部分も焼き魚や煮魚に活用できます。
また、スープや出汁をとる場合は、丸ごと買うのが経済的です。
タイやアラを丸ごと購入すれば、身を料理に使った後、頭や骨を活用してアラ汁や味噌汁を作ることができます。
特に、タイのアラは旨味が強く、出汁をとることでスープがより美味しくなります。


6.スーパーや魚屋の価格を比較する
魚を購入する際、切り身と丸ごとのどちらがコスパが良いのかを判断するには、スーパーと魚屋の価格を比較することが重要です。
同じ魚でも販売形態や店舗によって価格が異なるため、比較することでよりお得に購入できます。
例えば、スーパーではサバの切り身が100gあたり250円で売られていたとします。
一方、魚屋では1尾500gのサバが600円で販売されていることがあります。
サバの可食部の割合は約60%とされるため、丸ごと買った場合の可食部100gあたりの価格は200円になります。
この場合、魚屋で丸ごと購入するほうがコスパが良くなります。
ブリを例にすると、スーパーでは切り身が100gあたり300円で販売されていることがあります。
一方、魚屋では3kgのブリが6,000円で売られているとします。
ブリの可食部の割合が約50%と考えると、食べられる部分の価格は100gあたり400円となり、切り身のほうが割安になることもあります。
このように、魚の種類や販売価格によってどちらがコスパが良いかは変わります。
また、スーパーでは特売日やタイムセールを活用することで、さらにお得に購入できることがあります。
例えば、毎週木曜日に鮮魚コーナーが10%引きになるスーパーでは、その日を狙って買い物をすれば切り身の価格が下がります。
一方、魚屋では朝一番の仕入れ直後や閉店前に丸ごと買うと値引きされることがあるため、購入のタイミングも工夫すると良いでしょう。


7.さばくスキルや道具の有無を考慮する
魚を購入する際、コスパを考えるなら、切り身と丸ごとのどちらを選ぶかが重要ですが、さばくスキルや道具の有無も判断基準になります。
丸ごと買うほうが安く見えても、適切な道具がなかったり、さばくのに時間がかかったりすると、結果的に負担が増えてしまうことがあります。
例えば、タイを丸ごと購入すると、ウロコ取りや内臓の処理、三枚おろしが必要になります。
家庭にウロコ取りや出刃包丁がないと、作業がしにくく、キッチンも汚れやすくなります。
一方、切り身を選べば、そのまま焼いたり煮たりできるため、余計な準備が不要で、料理の負担が減ります。
忙しい共働き家庭では、切り身を選ぶほうが実質的にコスパが良くなることもあります。
また、ブリのような大型魚を一尾買うと、大きなまな板やよく切れる包丁が必要になります。
ブリは脂が多く、滑りやすいため、慣れていないとさばくのに時間がかかります。
三枚おろしにするにはコツが必要で、初心者には難しく感じることもあります。
一方、ブリの切り身やブロックを購入すれば、すぐに調理できるため、手間を省きながらも魚の栄養をしっかり取り入れられます。
アジやイワシなどの小型魚は、手で開くことができ、包丁を使わずに簡単に処理できます。
例えば、アジは手開きにしてフライや南蛮漬けにしやすく、イワシは丸ごと煮付けることで手間なく調理できます。
道具が少なくても扱いやすい魚なら、丸ごと買うことでコスパが良くなります。


8.骨の処理を考える
魚を購入する際、切り身と丸ごとのどちらがコスパが良いかを判断するには、骨の処理も重要なポイントです。
魚の骨の多さや取り除く手間によって、調理のしやすさや家族の食べやすさが変わるため、適した選び方をすることで負担を減らせます。
例えば、小さな子どもがいる家庭では、骨の少ない魚や骨抜き済みの切り身を選ぶと安心して食べられます。
鮭やタラの切り身は骨抜きされていることが多く、焼くだけで簡単に食卓に出せます。
忙しい朝のお弁当や、子どもが食べやすいおかずにするなら、切り身を選ぶことで調理の手間を省けます。
一方、ブリやサバなどの魚は、切り身で購入しても中骨が残っていることがあり、骨抜き作業が必要になります。
骨抜きを手間に感じる場合は、スーパーや魚屋で「骨抜き済み」のものを選ぶと負担が減ります。
ブリやサバは脂がのっていて美味しいですが、骨が多いため、小さい子どもや魚が苦手な人には食べにくいことがあります。
その場合、骨の少ない魚や加工済みの切り身を選ぶと食べやすくなります。
また、アジやイワシのような小型魚は、骨まで食べられる調理法が向いています。
例えば、アジを開いてフライや南蛮漬けにすると、骨まで柔らかくなり、そのまま食べられます。
さらに、イワシは圧力鍋で煮たり、味噌煮にすることで骨まで柔らかくなり、カルシウムをしっかり摂取できます。
骨の処理が面倒な場合は、骨まで食べられる調理法を活用するのも有効な方法です。


9.冷凍保存のしやすさを確認する
魚を購入する際、切り身と丸ごとのどちらがコスパが良いかを判断するには、冷凍保存のしやすさも考慮することが重要です。
適切に冷凍すれば、鮮度を保ちながら長期間保存でき、無駄なく活用できます。
例えば、切り身の魚は一枚ずつラップに包んで冷凍すると、必要な分だけ取り出して使えるため便利です。
特に、サーモンやタラのような魚は解凍後も食感が変わりにくく、焼き魚や鍋料理にそのまま使えます。
冷凍のまま調理できるため、忙しい朝や夕食準備の時短にもつながります。
一方、丸ごとの魚はそのまま冷凍するとスペースを取るため、事前に処理をしてから保存するのがポイントです。
例えば、大きなブリやタイは、購入後に三枚おろしにして小分けし、ラップで包んでから冷凍すると、調理がしやすくなります。
さらに、あらも冷凍しておけば、味噌汁や煮物に活用できるため、食材を無駄にせずコスパを向上させられます。
また、小型のアジやイワシは、頭と内臓を取り除いてから冷凍すると、解凍後すぐに調理できます。
例えば、アジを手開きして冷凍しておけば、フライや塩焼きにそのまま使えます。
イワシは手開きして塩をふってから冷凍することで、風味を保ちつつ、手軽に調理できるようになります。


10.調理経験に応じて選ぶ
魚を購入する際、切り身と丸ごとのどちらがコスパが良いかを考えるとき、調理経験に応じた選び方をすることで、負担を減らしながら美味しく魚を活用できます。
経験に合った魚を選ぶことで、調理のストレスを減らし、無駄なく食材を活かすことができます。
例えば、魚を扱うことに慣れていない場合は、切り身を選ぶと調理が簡単になります。
特に、鮭やタラの切り身は骨が少なく、焼くだけで簡単に食べられるため、忙しい家庭には便利です。
さらに、下処理が不要なので、包丁をほとんど使わずに済み、後片付けの手間も軽減できます。
少し魚の扱いに慣れてきたら、アジやイワシのような小型の魚に挑戦すると良いでしょう。
例えば、アジは三枚おろしにしてフライや刺身に、丸ごと塩焼きにすることもできます。
イワシは手開きしてフライや蒲焼きにすると、骨まで食べられる料理に仕上がります。
小型の魚は比較的簡単に処理できるため、練習にも適しています。
さらに、調理経験がある程度ある場合は、ブリやタイなどの大きな魚を丸ごと購入することで、コスパを最大限に高めることができます。
例えば、ブリは切り身にして照り焼きや煮付けに、アラは味噌汁や鍋の出汁として活用できます。
タイは塩焼きや蒸し料理に適しており、頭や骨も活用できるため、丸ごと買うことで経済的にもお得になります。


まとめ
魚の切り身と丸ごと、どちらがコスパが良いのかを判断するには、価格だけでなく、調理の手間や食べられる部分の割合も考慮する必要があります。
それぞれの特徴を理解することで、状況に応じた賢い選択が可能になります。
切り身の魚は、下処理が不要で調理が簡単なため、忙しい家庭や魚の扱いに慣れていない人に向いています。
特に、鮭やタラのように骨が少ないものは、小さい子どもがいる家庭でも安心して使えます。
ただし、丸ごとの魚と比べて価格が高くなる傾向があるため、頻繁に購入すると食費に影響が出ることもあります。
丸ごとの魚は、一見すると手間がかかるように思えますが、適切に処理すればコスパを向上させることができます。
例えば、アラを活用して出汁を取ったり、冷凍保存の工夫をすれば、長く使えて経済的です。
また、さばくスキルが身につけば、より多くの魚を選べるようになり、料理の幅も広がります。
どちらを選ぶかは家庭の状況や料理スタイルによって異なります。
手間をかけずに時短を優先するなら切り身、食費を抑えつつ活用の幅を広げたいなら丸ごと購入がおすすめです。
状況に応じた選択をしながら、無駄なく魚を楽しみましょう。
(※ご注意!ここで紹介しているデータは、2025年2月22日時点での独自による調査結果です。各データは、必ず運営会社発表のものと照合しご確認ください)




