生活クラブを始めてみたいと思っても、料金体系がよくわからず躊躇してしまう方は多くいます。出資金・商品代・配送手数料・会費といった複数の項目があるため、全体のイメージがつかめず、「何に、いくら必要なのか?」が不透明に感じられることが一番のネックになりがちです。
特に子育て中の共働き家庭では、サービスを選ぶ際に「毎月の負担が明確であること」が安心材料のひとつになります。今回は、生活クラブの料金体系を一つずつ丁寧に分解して解説しています。「出資金は返ってくるのか」「手数料は毎週かかるのか」「商品価格は高いのか」など、気になる点に的を絞ってお伝えします。
また、生活クラブ特有の「出資金」という考え方や、配送手数料が地域によって異なる点など、知っておくべき基本情報も含めて整理しています。実際の利用者の声をもとに、費用のイメージがしやすいよう構成しているため、これから始めたい方にも安心の内容です。
【要チェック】生活クラブ利用に必要な料金

生活クラブの利用には、「出資金」「固定費」「配送手数料」「商品代金」の4種類の費用が必要です。それぞれの役割や負担感を知っておくことで、安心して利用を始めることができます。
まず「出資金」は、生活クラブという組織に参加するための基本となる費用です。加入時に一定額を支払い、さらに毎月積み立てていきますが、これらは脱退時に返金される性質のものです。単なる支出ではなく、未来に戻ってくる“預け金”として捉えると負担感が和らぎます。
次に「固定費」が毎月発生します。地域によって多少の違いはありますが、情報誌の発行や地域活動、組合員どうしの助け合いに使われる費用です。額としては比較的少額で、数百円程度であることが多く、家計の中でも比較的無理のない出費です。
「配送手数料」は、商品を自宅まで届けてもらうための費用です。これは注文金額に応じて変動するしくみで、一定額以上の注文で無料になる地域もあります。また、子育て中の家庭や妊娠中の方は、手数料が無料になる特典制度が利用できる場合もあります。
そして「商品代金」は、実際に注文する食材や生活用品にかかる費用です。生活クラブでは、必要なものを必要なだけ注文するしくみになっているため、無駄な買い物を避けやすく、結果的に家計の管理がしやすくなります。品質にこだわった商品が多く、価格は安定しているため、安心感のある買い物が続けられます。
この4つの費用は、生活クラブを利用するうえでの基本ですが、制度や仕組みを理解しておけば、家計に無理なく取り入れることができるようになります。
個別料金について
1.出資金

生活クラブでは、サービスを利用する際に「出資金」が必要です。これは入会金や年会費ではなく、生協の活動を支えるために組合員が預ける資金であり、脱退時には返金される仕組みになっています。
加入時には1,000円の出資金が必要で、これに加えて毎月1,000円の積立増資を行います。いずれも将来的に返還されるため、単なる支出というより、預けておくお金と考えると安心です。たとえば3年間継続した場合、合計37,000円が積み立てられ、脱退時に全額戻ってきます。
出資金は、生協の運営基盤を支える大切な役割を持ちます。組合員の出資によって、共同購入に必要な倉庫や配送設備を維持したり、独自の安全基準に基づいた商品開発を行ったりすることが可能になります。安心で持続的な食の仕組みを支えるための資金です。
また、出資金は地域ごとに制度の細部が異なることがあります。たとえば東京都では「生活クラブ東京」と「地域ブロック生協」の両方に加入する形となり、それぞれに出資を行います。1口500円で、口数は地域のルールにより決まっていますが、いずれも返還対象です。
さらに、積立増資の金額は、標準は月1,000円ですが、一部地域では口数で選択できる場合もあります。家計状況に応じて柔軟に対応できる制度もあるため、加入時には確認するのがおすすめです。
出資金は一見すると負担に感じるかもしれませんが、返金制度があること、運営に役立つこと、そして家族の安心な食生活を支える仕組みに参加するという意味でも、納得して始めやすい制度です。
2.固定費

生活クラブでは、毎月少額の「固定費」が発生します。これは組合員としての基本的な負担であり、生活クラブの持続的な運営や安心の仕組みを支える役割を担っています。主に「エッコロ共済」「生活と自治」「コモンズ運営費」の3つが代表的です。
「エッコロ共済」は、組合員どうしの助け合い制度で、月額100円です。たとえば配達中の商品破損や、組合員活動中に起きた事故、イベント中の子どものケガなどが補償対象です。実際に利用した方の満足度も高く、安心感のある制度です。
「生活と自治」は、生活クラブが発行する情報誌の費用として月額100円かかります。商品へのこだわり、組合員の声、地域の活動情報などが掲載されており、生活クラブをより深く理解する手助けとなります。忙しい中でも目を通すことで参加意識が高まります。
「コモンズ運営費」は、地域ごとの運営費で、月額50〜150円と地域差があります。食育イベントやおためし会、組合員同士の交流会などの準備費用や、会場備品の維持費などに活用されています。子育て世代でも気軽に参加できる工夫がある活動です。
たとえば、年に数回開かれる手づくり調味料講座や、親子で楽しめる試食イベントなどは、この運営費によって支えられています。情報や活動の土台を支える費用として、納得できる使われ方をしているのが特徴です。
3つの固定費を合わせても、毎月250〜350円前後と少額です。家計に無理なく、生活クラブの制度や交流を身近に感じながら利用を続けられる仕組みです。
3.配送手数料
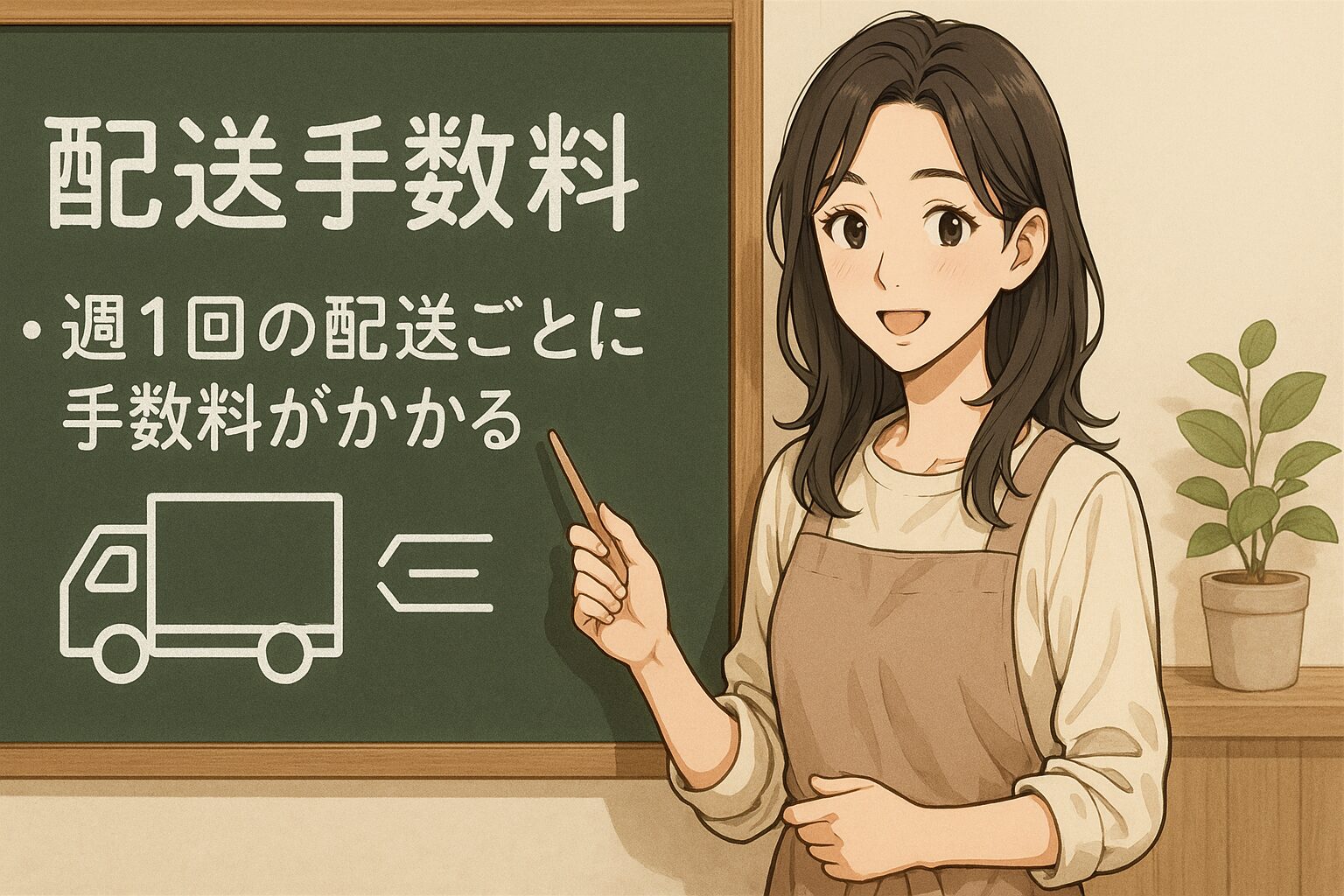
生活クラブの配送手数料は、個別配送を選んだ際に発生する費用です。週1回、自宅まで商品を届けてもらえる仕組みで、注文金額や家庭の状況によって手数料が変わります。内容を把握すれば、無理なく利用できます。
基本的には、1回の注文金額が3,000円(税抜)未満の場合、165円(税込)の手数料が発生します。逆に、3,000円以上注文すれば無料となる地域が多く、週ごとのまとめ買いを意識すれば手数料をかけずに使うことも可能です。冷凍食品や常温品を活用して、隔週で使う家庭も多くあります。
ただし、配送手数料の金額や無料となる注文金額の基準は、地域によって異なります。たとえば、神奈川県では2,000円以上で無料、千葉県や埼玉県では3,000円が基準になることが一般的です。加入前に、所属する地域のルールを確認しておくと安心です。
注文しない週は、手数料も一切発生しません。旅行中で不在だったり、冷蔵庫の在庫が多い週などは注文をスキップするだけで、無駄な出費を抑えることができます。スマホやパソコンから簡単に操作できるので忙しい家庭にも便利です。
妊娠中から未就学児を育てている家庭には、「子育て特典」が用意されており、申請すれば手数料が免除される制度があります。たとえば、3歳まで無料、あるいは6歳まで無料とする地域もあり、共働きの子育て世帯にとっては非常に助かる制度です。
さらに、新規加入後の一定期間(たとえば8週間)は配送手数料が無料となるキャンペーンもあります。実際に利用しながら、商品やサービスが自分に合っているか判断できるのは安心材料のひとつです。
受け取り方法も柔軟で、在宅不要の「置き配」に対応しています。保冷容器が使われるため、帰宅が夜になる日も安心です。オートロック対応マンションでも、管理人や指定場所に届けてもらえる場合があります。
4.商品代金

生活クラブの商品代金は、市販品と比べてやや高めな印象を持たれることがありますが、その裏には厳選された原料や丁寧な製造過程があります。食の安全や家族の健康を重視する家庭には、コストパフォーマンスの良さが実感しやすい設計です。
たとえば冷凍おかずセットは、主菜と副菜がセットになって1食あたり500〜600円程度。すべて国産食材を使用し、化学調味料・保存料は不使用です。仕事終わりでも温めるだけで栄養バランスのとれた食事が用意でき、外食を減らす効果にもつながります。
パンは国産小麦を使用し、イーストフードや乳化剤不使用。1袋300〜400円台で、冷凍保存も可能なためロスが出にくく、朝食用に常備する家庭が多くあります。品質が高く、子どもにも安心して出せます。
納豆や豆腐などの日配品も、添加物を極力使わない昔ながらの製法が基本です。納豆は3パック150円台、豆腐は1丁100円台から。毎日使うものだからこそ、信頼できる品質が重視されています。
調味料では、天然素材で作られた出汁パックや味噌が人気です。1袋500円前後ですが、香りや味に深みがあり、少量でも料理の満足度が高くなります。使用量が自然に減るため、結果的に長持ちします。
生活クラブでは週1回の定期注文が基本です。必要なものだけをリストで管理しながら注文するため、衝動買いや買いすぎが起こりにくく、家計管理のしやすさにもつながります。
安さよりも「安心して継続できるかどうか」で判断することで、生活クラブの商品代金の納得度は大きく高まります。使い方次第で費用対効果は十分に見込める内容です。
【これは知っておきたい】生活クラブの利用料金を節約する方法5選
1.プレママ&ママ特典を利用する

生活クラブの「プレママ&ママ特典」は、出産前後の家庭を対象に配送手数料を免除する制度で、継続利用時の負担を大きく軽減します。対象期間中は注文金額に関係なく手数料がかからないため、少量注文や頻度調整がしやすく、忙しい子育て世帯にとって非常に実用的です。
通常、生活クラブの配送には週1回あたり165円(税込)の手数料がかかります。これが妊娠中からお子さんが3歳または6歳になるまでの間、完全無料になります。たとえば離乳食づくりに必要な無添加冷凍野菜や、手軽に栄養が摂れるレトルトパウチなどを少しずつ頼む家庭では、毎週使っても追加費用が一切発生しません。
東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県など多くの地域で導入されており、申請方法は加入時にWEBや書面で必要事項を記入するだけ。更新の必要がない地域も多く、一度登録すれば数年間そのまま利用できます。
節約効果は高く、年間換算で8,000〜10,000円相当がカットできる試算です。これはベビー用品やミルク代に回せる金額であり、実際に制度を利用した家庭では「最初から申し込んでおいて良かった」と実感する声も多く聞かれます。
また、制度利用前に「プレママお試しセット」で生活クラブの商品を体験することもでき、約1,000円前後で人気商品が詰まったセットを注文できます。内容には国産素材のおかずや冷凍惣菜、調味料などが含まれ、実際に口にして判断できる安心感があります。
育児中は体力的・時間的な制約が大きくなり、日常の買い物すら負担になることがあります。そんな中、この特典を利用することで、利用料金の一部を実質的に削減しながら、安心して生活クラブを継続する基盤が整います。
2.まとめ買いで配送手数料を無料にする

生活クラブでは、一定金額以上の注文で配送手数料が無料になる仕組みがあり、週1回のまとめ買いを意識することで、無駄な出費を抑えることができます。多くの地域では注文金額が3,000円(税抜)以上であれば、1回あたり165円(税込)の配送手数料が無料になります。毎週165円がかかると、月あたり約660円、年間では約8,000円近くの支出となるため、この金額が抑えられることは家計への効果が大きいです。
たとえば冷凍食品をまとめて購入することで、1回の注文で3,000円を超えやすくなります。冷凍餃子・うどん・冷凍野菜・唐揚げ用の鶏肉などを組み合わせれば、2週間分の食材が無駄なく揃い、買い物に行く手間も省けます。忙しい平日の夕食準備にも役立ちます。
また、牛乳・卵・ヨーグルトといった日配品に、トイレットペーパーや洗剤、子ども用おしりふきなどの日用品を組み合わせると、自然に注文金額が上がります。生活必需品を計画的にまとめて頼むことで、送料無料のハードルを無理なくクリアできます
。
さらに、味噌・醤油・だしパック・乾麺など、保存がきく商品を中心に選べば、冷蔵庫に余裕がある週でも3,000円以上の注文がしやすくなります。調味料は毎日少しずつ使うため、余らせることなく効率よく使い切ることができます。
注文内容をあらかじめ家族で話し合ってリスト化することで、無駄な注文を防ぎ、必要なものを効率よくまとめられます。買い忘れも減るため、追加の買い物による衝動買いも防げます。
たとえば、冷凍食品と日用品で2,500円に届かなかった週でも、少しだけ追加で注文すれば手数料が無料になります。あと一品の選択肢としては、ストック用のおやつや飲料、紙類などがおすすめです。
無理に高額な商品を追加するのではなく、いつか必要になるものを少しずつ加えるスタイルが無理なく続けられるコツです。配送手数料を意識して買い方を見直すことで、日々の暮らしが整い、時間とお金のゆとりが生まれます。
3.配送手数料無料期間をフル活用する
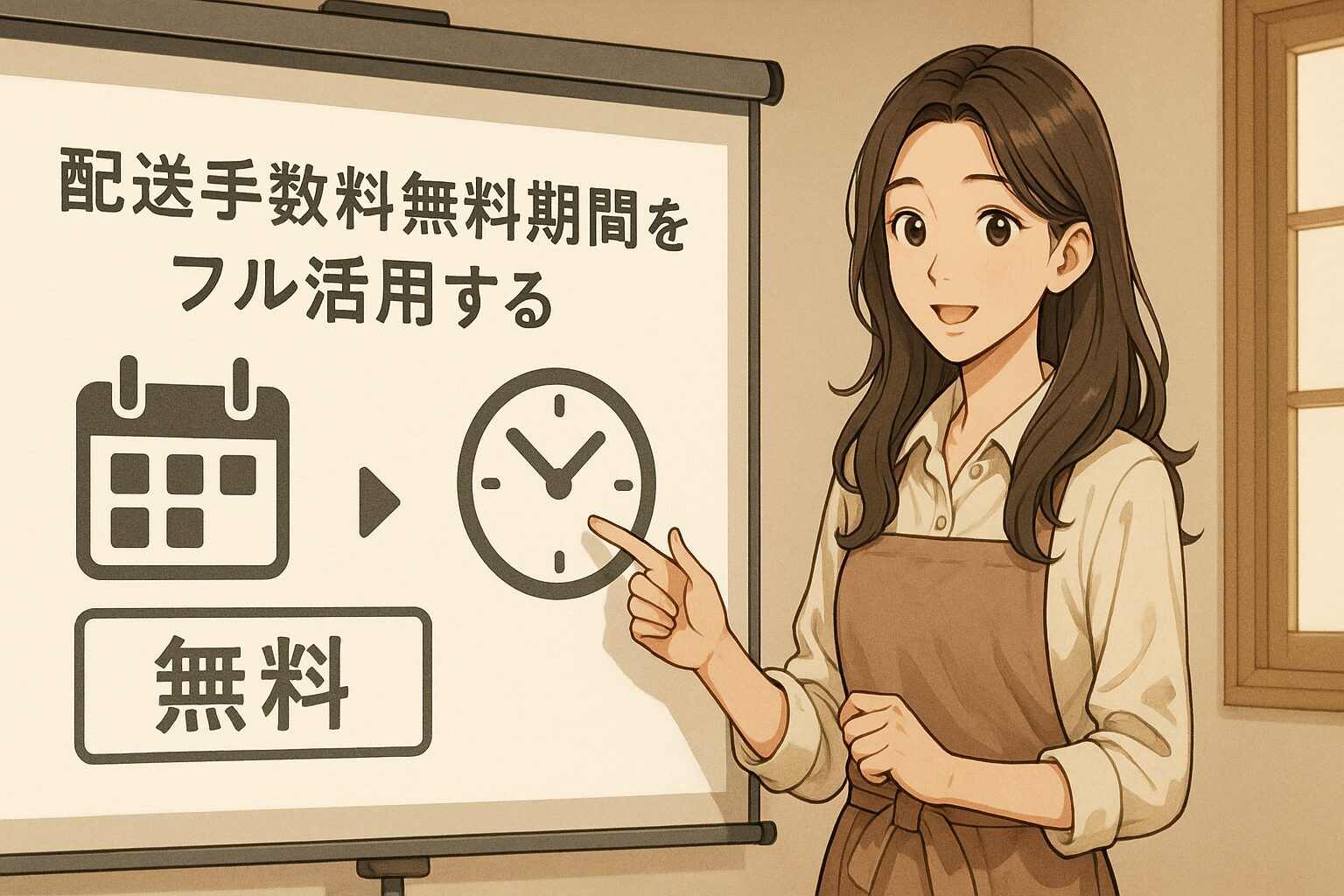
生活クラブでは、新規加入者に対して一定期間、配送手数料が無料になる特典があります。この無料期間を最大限に活用することで、初期の利用料金を大幅に抑えることができます。特に共働きで子育て中の家庭にとっては、手数料がかからないことで気軽に試せる環境が整い、無理なく生活クラブを始められるメリットがあります。
無料期間は地域によって異なりますが、最大1年間配送手数料が無料になります。この期間中は、通常1回あたり165円(税込)かかる手数料が毎週0円になるため、最大で8,580円の節約につながります。
たとえば、加入直後の週に冷凍食品をまとめて注文すれば、冷凍庫に余裕のあるうちにストックを充実させられます。冷凍うどんや唐揚げ、冷凍野菜、魚の切り身などは賞味期限も長く、忙しい平日の夕食準備にも役立ちます。
また、日用品の買い足しをこの期間に集中させるのもおすすめです。トイレットペーパー、洗濯洗剤、ティッシュなどのかさばる商品を複数回に分けて購入しても、追加の手数料がかかりません。
さらに、お菓子やレトルト食品、缶詰などの常温保存品を試しながらお気に入りを見つけるのもこの時期が最適です。いろいろな商品を少しずつ試しても手数料がかからないため、注文に対するハードルが下がります。
この期間を利用して、家族構成やライフスタイルに合わせた注文リズムをつかめば、不要な注文を避け、効率よく必要な品を選ぶ習慣づくりにもなります。無料期間で得られた注文パターンは、有料期間が始まったあとも無理のない継続につながり、結果的に長期的な節約効果が期待できます。
このように、配送手数料無料期間は生活クラブの導入期を支える重要な仕組みです。最初の数週間を賢く使いこなすことで、日々の暮らしと家計のバランスを整える良いスタートが切れます。
4.ペア配送、班配送を利用する

生活クラブでは、配送手数料を節約する方法として「ペア配送」「班配送」の仕組みが用意されています。これは、近隣の利用者と一緒に配達を受けることで、個別配送よりも手数料が安くなる仕組みです。共働きで子育て中の家庭にとっては、無理なく固定費を抑える手段の一つです。
ペア配送は、同じ建物や近所の家庭と二人一組で受け取るスタイルです。たとえば同じマンションの別の階に住むママ友と一緒に登録すれば、配達ルートが一本化され、個別配送よりも手数料が安くなります。地域によって異なりますが、手数料が半額になる場合や、一定条件で無料になることもあります。
班配送は、3人以上のグループでまとめて一箇所に配送する形式です。公園や集会所、特定の自宅玄関などにまとめて置いてもらうことで、手数料が完全に無料になることもあります。たとえば週1回、同じ保育園のママたちで一箇所に集めて受け取るようにすれば、家計に負担をかけずに生活クラブを利用できます。
これらの仕組みを活用すれば、年間で5,000円~8,000円ほどの節約が可能になります。浮いたお金を別の食費や日用品費に回すことができるため、全体の支出を抑えることにもつながります。
また、配達日時をあらかじめ調整できるため、不在がちでもスムーズに受け取れるのもポイントです。班内で交代で受け取るなど、柔軟な体制を組めば、忙しい平日でも安心です。
特に育児中の家庭では、荷物の受け取りや仕分けが負担になることもありますが、ペア配送・班配送を活用することで、負担を分散させつつ節約も実現できます。
配送先を共有することで、ドライバーの移動距離が短縮され、環境にも優しいという副次的なメリットもあります。また、配送時間も安定しやすく、計画的に受け取りができるようになるため、生活リズムの安定にもつながります。
最初は気が引けるかもしれませんが、実際に利用している人の多くが「もっと早く知っていればよかった」と感じており、利用率の高い地域ではごく一般的な方法として定着しています。特に近所に知り合いがいる場合は、声をかけて一緒に始めてみると想像以上に簡単です。
5.お試しセットで満足度をチェックする

生活クラブを始める前に「お試しセット」を活用することで、無駄な出費を避けながら実際の商品やサービスの満足度をチェックできます。通常よりも大幅に割引された価格で人気商品を体験できるため、コストを抑えて納得してから本格利用をスタートできます。
たとえば、冷凍餃子や国産鶏の唐揚げ、だしパック、ポークウインナーなど、日常の食卓に登場するアイテムが数品入って1,000円前後で提供されます。どれも素材や味にこだわった生活クラブ自慢の品ばかりで、実際に食べてみることで品質の高さが実感できます。
実際に試して「子どもが喜んで食べた」「時短調理ができて助かった」「スーパーと比べてもコスパが良い」と感じられれば、安心して加入後の注文に踏み切れます。逆に「味が好みに合わない」と感じた場合も、事前にわかることで無駄な出資金や手数料の支払いを避けられます。
さらに、お試しセットには冷凍食品や常温保存ができるものも多く含まれているため、届いたその日に使わなくてもムダになりません。仕事や子育てに忙しい時期でも、冷凍庫やパントリーに入れておくだけで安心です。
使い方に慣れるきっかけにもなるのが大きなポイントです。たとえば注文カタログの見方やWEB注文の流れ、配達の仕組みなども、試しながら理解できます。実際の注文に進む前に一連の流れを体験できるため、初心者でも安心してスタートできます。
また、お試しセットを注文すると、地域の担当者からのサポートや案内が受けられることもあります。質問や不安を事前に解消しやすくなるので、加入後のトラブル回避にもつながります。
また、セット内容のバランスも工夫されており、「冷凍・加工品・調味料」といった異なるカテゴリの商品が組み合わされています。これにより、生活クラブの商品の特徴を幅広く体感でき、購入の判断材料として非常に役立ちます。
実際に使ってみた上で「毎週頼みたい」「これは継続的に使えそう」という感覚が得られれば、ムダな買い物や注文ミスを減らすことにもつながります。入会前に納得のいく体験をしておくことが、長く使い続けるための鍵となります。
まとめ

生活クラブを使ってみたいけれど、料金がよくわからないという不安は、利用前にしっかりと情報を整理することで解消できます。出資金・商品代・配送手数料・会費といった構成要素をひとつずつ分けて見ていけば、実際にどれくらいの費用がかかるのか、自分にとって無理のない利用方法が見えてきます。
特に子育てや共働きの家庭では、毎週の注文スタイルやお試しセットでの事前確認など、費用を把握しやすくする工夫もポイントです。「高そう」というイメージだけで判断せず、自分の家庭のライフスタイルと照らし合わせて検討することが、安心して利用を始める第一歩につながります。
料金の仕組みがはっきりすれば、生活クラブの魅力もより実感しやすくなります。配送スタイルの選択や特典制度の活用によって、無理なく家計に取り入れる方法も多数存在します。正しい情報を得て、納得できるスタートを切ることが、賢い選択につながります。
共働きで忙しい家庭ほど、無駄な出費を避けながら、必要な分だけ取り入れるスタイルが向いています。とくに気をつけたいのが、利用開始前に費用の内訳をしっかり確認しておくことです。どのタイミングでどの金額が発生するのか、地域ごとのルールの違いなども含めてチェックしておくと、あとから「こんなはずじゃなかった」と感じるリスクが減ります。迷ったときは公式サイトだけでなく、地域担当者に直接問い合わせてみることもおすすめです。
(※ご注意!ここで紹介しているデータは、2025年5月3日時点での独自による調査結果です。各データは、必ず運営会社発表のものと照合しご確認ください)








