コープきんきの「退会」、実際にスムーズに進められるのか気になりますよね。今回は、初めて退会を検討するママや共働き家庭のために、必要な段取りと注意すべきポイントをやさしく整理しています。
まず、退会手続きの実際の流れや窓口の混雑状況を踏まえ、スムーズに進める方法を具体的な事例とともに紹介。書類提出や電話連絡のタイミングなど、主婦のリアルなキャンセル事情に寄り添いながら解説します。
次に、出資金やポイント、クーポンなど退会と同時にどう扱われるか、知っておきたいルールを簡潔にお伝え。得したつもりが、損してしまうケースを防ぐための工夫も。
さらに、「休止との違い」や「再加入時の手続き」など、事情が変わる中でも、ムダなくメリットを活かす判断基準を整理。備えておけば、退会後もリスタートがスムーズです。
これから退会を検討する方へ、安心して決断できるように、必要な情報を一つずつ丁寧に手渡します。最後までご一読いただくことで、「コープきんき卒業」の時期にも前向きになれるはずです。
申し込み前に知っておきたい!コープきんき退会のルール
1.退会には「脱退申請書」の提出が必要

コープきんきの退会には「脱退申請書」の提出が必要です。電話や配達員、あるいはeフレンズ・アプリ経由で申請書を取り寄せ、必要事項を記入して提出することで手続きが始まります。
具体的には、一般的に以下のように進めます。
- 電話窓口や配達担当者に「脱退申請書を送ってほしい」と依頼
- 郵送または配達時に申請書が届くので、自宅で必要項目(組合員番号・氏名・退会希望日など)を記入
- 署名や押印が必要な場合もあるので、忘れずに記入
- 配達担当者へ手渡し、またはカタログ折込封筒や郵送で提出
例えば、転居や共働きで生活が変わるタイミングで退会を検討する際、この手順をクリアすることで、スムーズにシステムから外れられます。子どもが幼稚園に入園して生活スタイルが変わったタイミングで退会を選んだ家庭では、電話で脱退申請書を取り寄せ、届いた翌週に提出。2~3週間後には出資金の返金も完了し、手続きはスムーズに進みました。
注意点として、脱退申請書を提出した週での注文分までが最終の利用分となるため、退会希望日は配達スケジュールに合わせて決めるとムダがありません。
また、eフレンズ・アプリ経由で申請書を取り寄せた場合、紙が届いてから内容を確認して記入、返送する必要があります。ネット上で即時完了、というわけではないので、余裕を持ったスケジュール調整が大切です 。
さらに、「退会するか迷っているけれど、まずは一時休止したい」という場合は、脱退申請書ではなく「配達休止」の申し込みも可能。状況に応じた選択で安心して手続きできます。
忙しい中でも、脱退申請書を取り寄せて記入・提出する手順がクリアになれば、退会後の後悔も少なくなります。特に出資金返還のタイミングや期限も確認しながら進めることで、予定通りに手続きを完了でき、家計の見通しも忘れずに整います。
2.退会には、「法定脱退」「自由脱退」の2種類がある
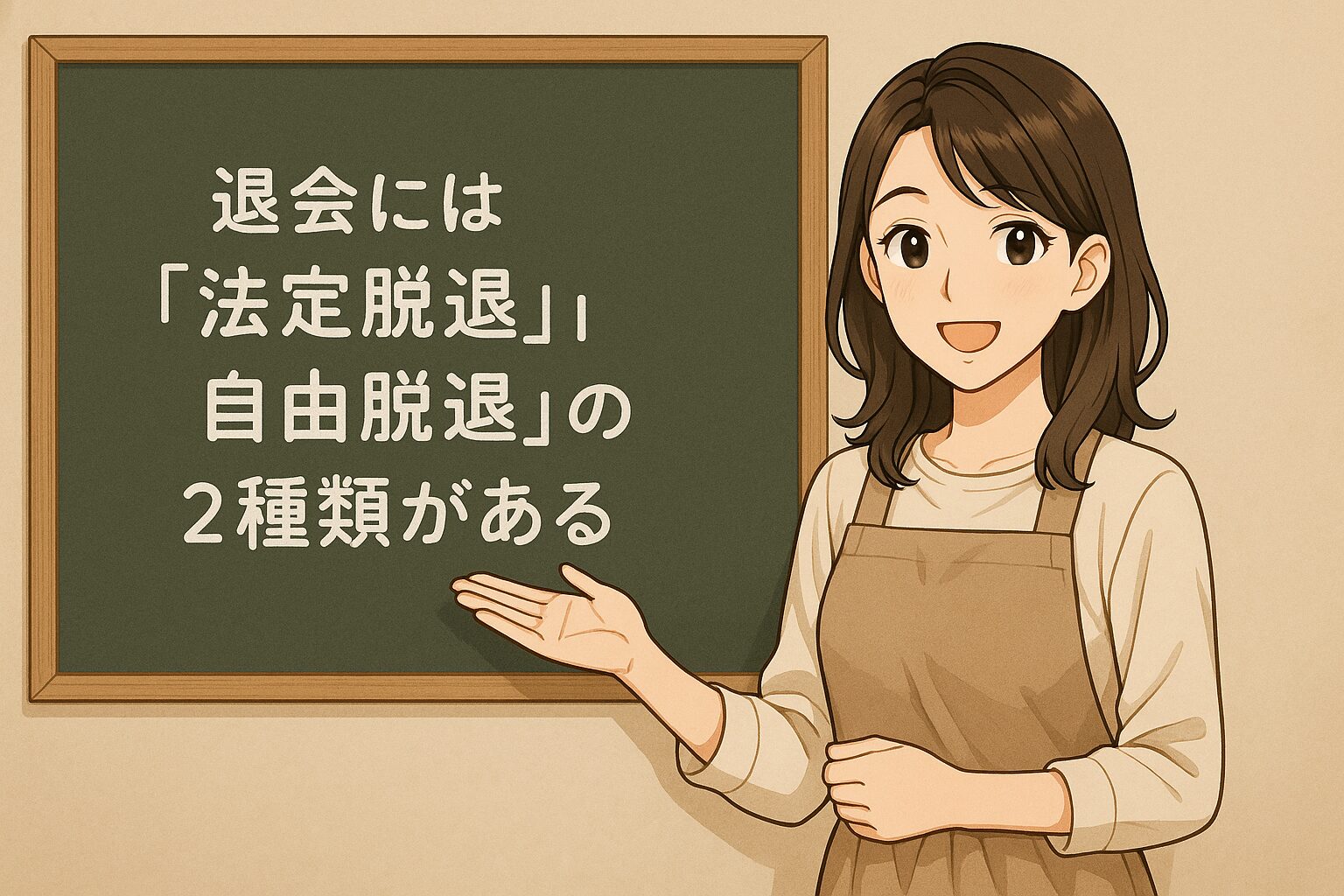
コープきんきの退会には、大きく分けて「法定脱退」と「自由脱退」の2種類があります。
法定脱退は、「転居などで配達エリア外になった」「ご本人が亡くなった」など、制度上退会が必要になるケースです。例えば、共働きで家族と一緒に県外に引っ越す場合や、高齢者の親御さんが亡くなったときなどが該当します。こうした理由なら、配達停止と同時に手続きを進められるため、出資金は手続き後約2〜3週間で返金されやすく、比較的スムーズです。
一方、自由脱退は「生活スタイルが変わって利用頻度が減った」など、個人の判断で退会する場合に該当します。たとえば、子どもが大学に進学して家族の食事情が変わったり、週末だけの利用になり「もう続けなくてもいいかも」と感じたときなどです。この場合、事業年度末の90日前(例:12月末までに手続き)までには申請が必要で、出資金は翌年度末(例:3月下旬以降)に返金されます 。返金までの期間が長いため、計画的に申請することが重要です。
実際の活用例はこんな感じです。
- 夫の転勤で県外へ引っ越す→法定脱退で「脱退申込書を提出」→3週間後に出資金が振込まれ安心
- 子どもの独立で利用スタイルが変わる→自由脱退を12月中に申請→翌年3月末に返金されライフスタイルの変化に対応
- 利用頻度が減って退会を決める→自由脱退で申請→出資金が戻るまで数ヶ月かかることを見越して申請
どちらの退会方法を選ぶにしても、「いつまでに」「どんな理由で」「いつ返金されるか」をママとしてスケジュールに組み込んでおくと、退会後も後悔せずスムーズです。手続き前に、この2つの違いをしっかり確認しておきましょう。
3.退会申請は電話・配達員・支所・店舗で可能

コープきんきを退会する際は、「脱退申請書」の手続きをどこで行うか把握しておくと安心です。電話、配達担当者への依頼、支所や店舗での対応など、都合にあわせて選べます。この柔軟性が、忙しい共働きママにとって大きな助けになります。
たとえば、「市販の宅配に切り替えたい」と思った場合は、まず電話で「退会したい」と伝えるだけでOK。数日後に申請書が自宅に届き、届いた週の配達時に担当者に渡すと、スムーズに手続きが進みます。同様に、「配達員さんに直接話したい」と思ったら、配達日に「退会申請書をください」と伝えれば、その場で書類を手渡ししてもらえます。
また、支所や店舗(サービスカウンター)に行けるときには、「退会手続きをお願いします」と伝えれば、その場で申請書を受け取ることが可能です。休日にショッピングのついでに立ち寄ってスタッフに事情を話せば、用意してくれる仕組みです。
さらに、引っ越しを機に退会したご家庭では、「配達員に退会申請書を渡し、出資金の返金手続きが完了」した事例があります。転居前後の慌ただしい状況でも、担当者に直接相談できることで安心感につながったと聞きます。
利用頻度が減って「少しお休みしたいな」という場合には、退会ではなく「配達休止」も選べます。こちらも電話や店舗で相談するだけで対応できるので、手間なくスキップできます。
こうした選択肢があることで、コープきんきは気軽に始めやすく、またいつでもやめやすい点が評価されています。特に子育てや仕事のリズムが変わるタイミングでも、相談しやすい窓口があるのは心強いですね。退会や休止の判断に迷ったときは、まず配達担当者に一声かけてみてください。最適な手続きを一緒に考えてくれます。
4.退会申請には「組合員証」「出資金証書」「身分証明書」「通帳など口座情報」が必要

コープきんきを退会する際には、いくつかの書類を事前に準備しておくと手続きがスムーズに進みます。
まず必要になるのが「組合員証」です。これは加入時に配布されたカードや紙面で、組合員であることを証明するものです。なくしてしまった場合でも、再発行や代替措置が取られることが多いので、慌てずに問い合わせてみてください。
次に必要となるのが「出資金証書」です。これは出資金の金額や履歴を示す重要な書類で、出資金の返金手続きの際に必要です。万が一紛失している場合は、コープきんきの支所や担当者に再発行の相談ができます。
さらに、「本人確認書類」の提示も求められます。運転免許証やマイナンバーカード、健康保険証などが一般的に利用されています。現住所と一致していることが確認できる書類を用意しておくと安心です。
そして、出資金の返金を受け取るための「通帳」や「口座情報がわかる書類」も必須です。金融機関名、支店名、口座番号などがわかるものであれば問題ありません。
実際に、ある利用者はこれらの書類を一式そろえた状態で手続きを進めたところ、申請から2週間ほどで完了し、返金までスムーズに進んだという例もあります。
退会は一度きりの手続きだからこそ、書類の準備がしっかりしていれば安心して進められます。忘れ物のないよう、事前に確認しておくことが大切です。
5.共済に加入している場合は、別途解約手続きが必要
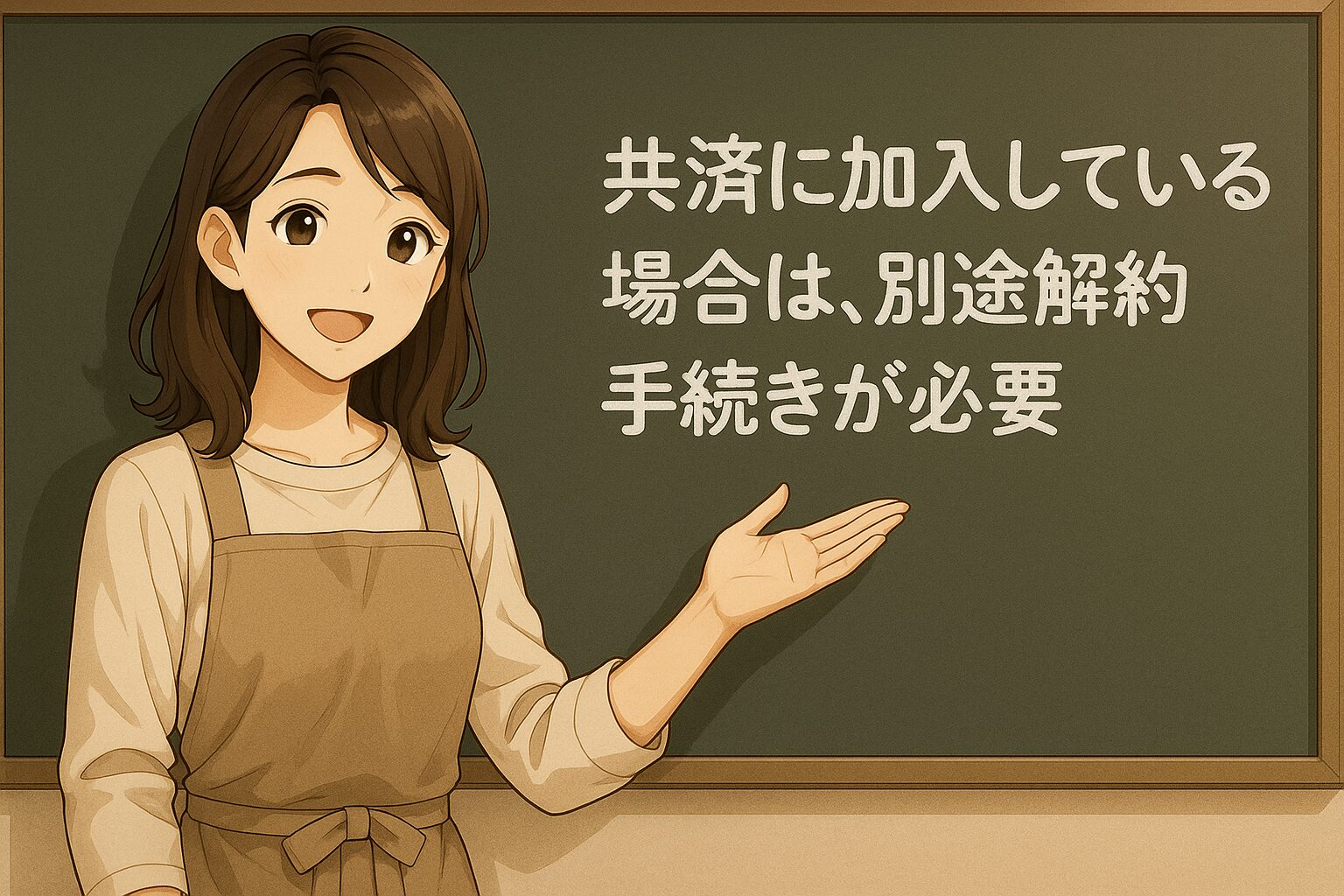
コープきんきを退会前に共済にも加入している場合は、別途共済の解約手続きが必要です。
共済は生協に加入していることが前提のサービスで、宅配をやめても自動で解約にはなりません。退会後に「いつまで共済に入っていたのか」が不明確なまま掛金が継続されることもあるため、事前確認がおすすめです。
共済を解約するには、コープ共済センター(コールセンター)へ連絡し、解約申請書類を取り寄せる必要があります。書類には契約者名や契約番号、解約希望日などを記入し、指定期日までに返送または窓口へ提出します。たとえば、掛金が月末に振替されるタイプの共済では、解約月の末日までに書類が届くようにする必要があります。
具体的には、
- 夫の転勤で引っ越す際、共済も解約。コープ退会前にコールセンターへ連絡し、翌月分の掛金が止まりました
- 子どもの独立で共済が不要になった家庭では、書類を郵送し、翌月末には共済解約通知が届いて安心して手続きできました
- パートからフリーランスになり収入が変動したママは、窓口で手続き後、掛金振替がストップ。以降、請求が来なくなったと報告がありました
共済ごとに解約書類の提出期限や切替日のルールが異なるため、契約中の商品がある場合は「いつまで共済に入り、いつ辞めるか」を先に整理してから手続きを始めると安心です。
退会と解約のタイミングを揃えておけば、掛金のムダ払いを避けられ、スッキリと退会できます。
6.出資金の返還タイミングは脱退理由によってが変わる

コープきんきを退会するときには、「出資金の返還タイミングが脱退理由によって変わる」点を事前に把握しておくことが重要です。安心して進めるためにも、具体的なケースとスケジュールで理解しておきましょう。
まず、転居や本人死亡といったやむを得ない事情で退会する「法定脱退」の場合は、申請後約2〜3週間ほどで出資金が返金されるケースが多いです。たとえば、県外へ家族ごと引っ越した家庭では、退会申請書を提出してから3週間後に指定口座へ振り込まれ、「急な環境変化の中でも安心でした」と話す方もいらっしゃいます。
一方、「自由脱退」は自分の都合による退会で、事業年度末の90日前まで(例:12月末まで)に申請すると、その年度末(3月末)以降、翌年度開始後に返金されます。たとえば、子どもの進学を機に利用頻度が減った家庭では、12月中に申請→翌3月返金という流れを取ることで、「趣味の出費にまわせた」と喜ばれています。
さらに、減資(一部払い戻し)を希望する場合も、同じく年度末の90日前までに手続きが必要で、返金は翌3月以降になります。たとえば、毎月の負担を減らしたい家庭では、余裕のある時期に少しずつ減資し、必要な時に戻す工夫をされています。
このように、「法定脱退」では2〜3週間で、「自由脱退」や「減資」では3月以降と、返金までの時間に大きな差があります。退会の意思が固まったら、「どちらの理由で」「いつ申請するか」「いつ返金されるか」をスケジュール帳に記しておくと、焦らず手続きが進められます。
特に子育てや仕事の区切りのタイミングでは、先を見据えた計画が大切です。出資金は「戻ってくるお金」ですから、申請条件と時期に注意すれば、無駄なく安心してコープきんきから卒業できます。
7.配達終了(休止)制度もあり、退会せずに一時停止可能

配達をしばらくお休みしたいときは、退会せずに「配達終了(休止)制度」を使えば手続きは最小限です。電話・配達員・支所のいずれかに「○月○日から休止したい」と伝えるだけで、最長6か月まで配送をストップできます。
たとえば妊娠後期に実家へ里帰りする場合、出発2週間前に電話で休止連絡を入れると、予定日に合わせて自動で配達が止まります。戻ってきたら「来週から再開したい」と再度連絡するだけで従来の曜日・時間帯に配達が再開され、カタログも同時に届きます。
もう一例は、家族で2か月間の長期旅行に出るケース。出発前に配達員へ直接「この期間を休止で」と伝えると、掛金や手数料は発生せず、旅行先での無駄な請求を防げます。帰国後も出資金はそのまま維持されるので、再加入手続きは不要です。
さらに年度末の繁忙期で買い物の時間が読めないときは、3週間だけ休止し、忙しさが落ち着いてから再開することも可能です。共働き家庭が「使う週・止める週」を柔軟に選べるため、家計管理がしやすくなる点もメリットです。
休止中はポイントや共済契約がそのまま残るので、出資金や保障を失う心配もありません。配達再開月には自動的にカタログが送られてくるため、注文を忘れるリスクも抑えられます。
退会してしまうと出資金返還や再加入手続きに時間がかかりますが、休止なら書類提出は不要で最短1回の電話で完了します。生活リズムが変わりやすい子育て世帯にとって、退会より休止を選ぶことで手間と費用の両方を節約できます。
8.退会後再加入する場合は出資の再申請が必要
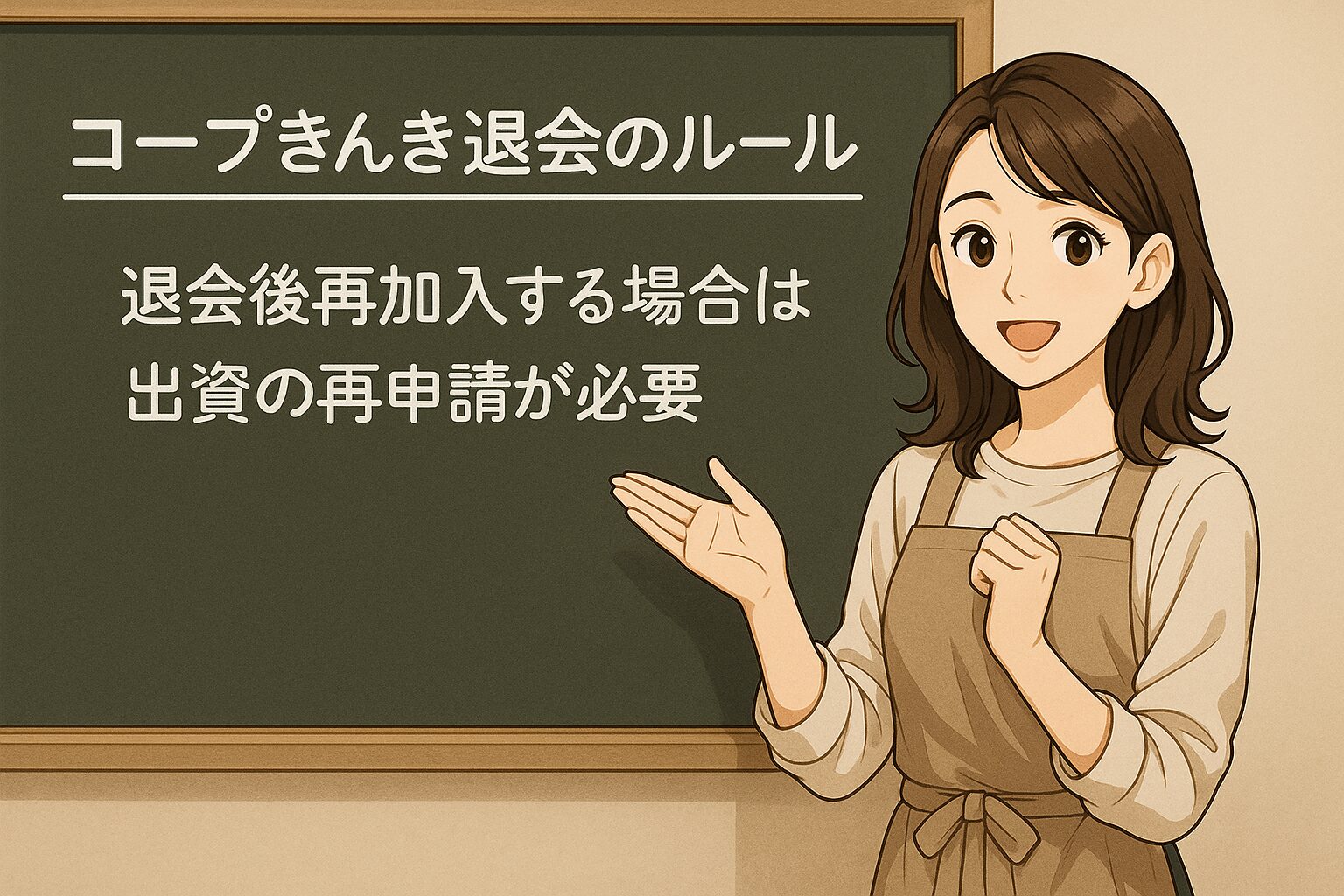
退会後にコープきんきを再利用したいときは、出資金を改めて預け入れ、組合員資格を取り直す必要があります。退会時に返金された出資金はリセット扱いとなるため、再加入時には最低一口500~1,000円を新たに申請する仕組みです。電話または資料請求フォームから加入申込書を取り寄せ、氏名・口座・希望口数を記入し、配達員や支所へ提出する流れは初回と同じです。
たとえば、夫の転勤でいったん法定脱退した家庭が三年後に同じ地域へ戻ったケースでは、出資金1,000円を再申請し、翌週から以前と同じ曜日に配達が再開されました。
二つ目の例は、育休復帰で利用頻度が下がり自由脱退したものの、小学校入学で忙しさが増して再加入した家庭です。出資金500円を電子マネーで支払い、休止前に貯めたポイントはゼロになりましたが、紹介キャンペーンで1,000ポイントが付与され実質負担をカバーできました。
三つ目は、実家への長期帰省で六か月の休止を選ばず退会した利用者が、わずか二か月後に再申込みをした例です。出資金800円を再預託する形となり、「休止を選べば出資金を動かさずに済んだ」と後悔したといいます。
再加入だからといって審査が厳しくなることはありませんが、以前の組合員番号や注文履歴は引き継がれず、アプリ設定やお気に入り登録は再度行う必要があります。共済やポイント制度も新契約扱いとなるため、保障の空白期間を作りたくない場合は退会ではなく休止制度を活用するほうが安心です。
出資金は退会・再加入のたびに動きます。ライフスタイルの変化が一時的か長期的かを見極め、休止制度との違いを理解しておくことが家計管理のカギになります。
9.eフレンズ(ネット注文)からは退会申請ができない

eフレンズ(ネット注文)からは退会申請ができません。申請は電話、配達担当者、支所または店舗窓口でのみ受け付けられています。ネット上の注文画面やお問い合わせフォームには退会機能がないため、まずは対面や電話で申請手続きを行う必要があります。
たとえば、夜間に「ネットからできるかな」と試みたママがいたそうですが、eフレンズに退会ボタンが見つからず不安に。「調べたところネットでは申請不可」とわかり、翌日電話相談したところ、「ご安心ください、申請書を郵送します」と案内され、スムーズに解決しました。
また、共働き家庭でダブルワーク中のママは、配達担当者に対面で事情を伝え、申請書を直接受け取ってその日のうちに記入・返却。これにより、忘れることなく当週中に申請が完了し、翌週から配達がストップできました。
さらに、ショッピングモール内にある支所で申請した家庭もあります。お子さんのお迎えついでにカウンターへ立ち寄って「退会したい」と伝えたところ、ワンストップで申請と確認までその場で終了。eフレンズを通さずとも、店舗窓口で簡単に手続きでき安心でした。
解決法は「ネットで完結できない」ことを前もって知ること。電話一本か配達時の一言で開始できる手続きなので、忙しい共働きママでも混乱せず落ち着いて進められます。eフレンズは日常の注文に便利ですが、退会に関しては「対話」が必要な仕組みであることを理解しておくと安心です。
コープきんきをスムーズに退会するためのポイント
1.出資金の仕組みと返金タイミングを確認しておく
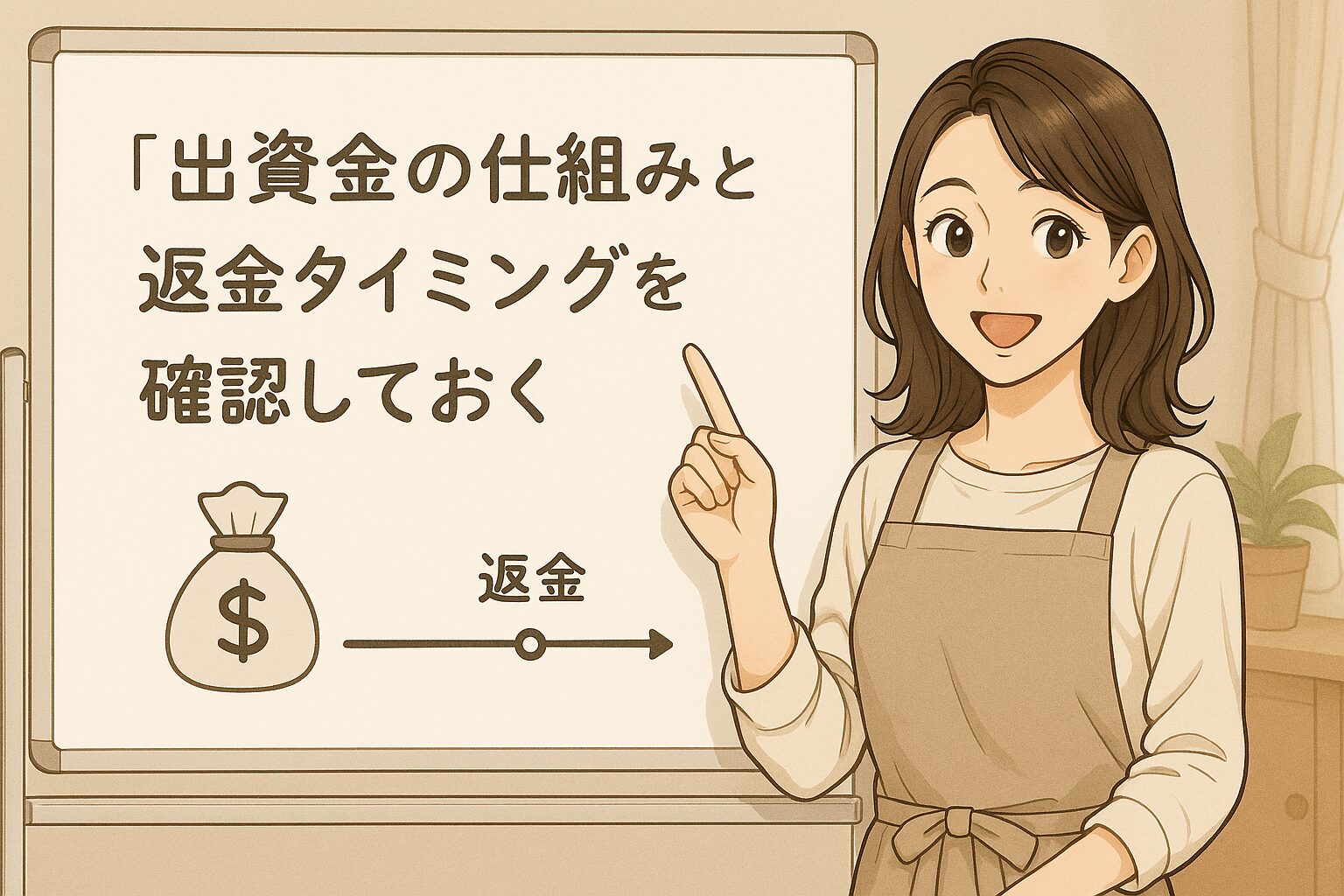
出資金は、コープきんきを退会する際の返金の要ともなる大切なお金です。ライフステージが変わる可能性がある共働き子育て家庭では、出資金の仕組みと返金タイミングを事前に確認しておくことがポイントです。
まず、出資金は加入時に預けるお金で、退会時に返金されます。法定脱退(引越しや死亡など不可抗力)では脱退手続き後、2~3週間程度で指定口座に振り込まれるケースが多いです。たとえば、夫の転勤で急遽家族で県外へ引っ越した際、この迅速な返金により「新生活の資金をすぐ確保できた」という声が寄せられています。
一方、自由脱退(自己都合)は、脱退届を事業年度末(12月末)の90日前までに提出する必要があり、通常は翌年3月~4月に返金されます。たとえば、子どもの進学で利用頻度が減ることを見越して12月中に退会申請した家庭では、年度末にまとまった額が口座に戻り、「春からの学用品費に充てられて助かった」という実例もあります。
さらに、自由脱退ではなく減資(一部返金)を選択する場合も同じ時期の返金になります。例えば、育休中に少し手元を軽くしたい場合、年末までに申請すれば翌春に希望額が口座に返ってきます。
このように出資金の返金時期は、「何を理由に退会するか」で大きく変わります。急な引越しなどにはすぐ返ってくる「法定脱退」、一方で家計整理が目的なら「自由脱退・減資」の申請スケジュールを押さえることが重要です。
そのため、退会を検討するタイミングが近づいたら、「自分はどの理由で、いつ申請すればいつ返ってくるか」をすぐに答えられるようにしておくことが、スムーズな退会と家計管理につながります。
2.退会時に必要な書類(脱退申込書)の入手方法を把握しておく
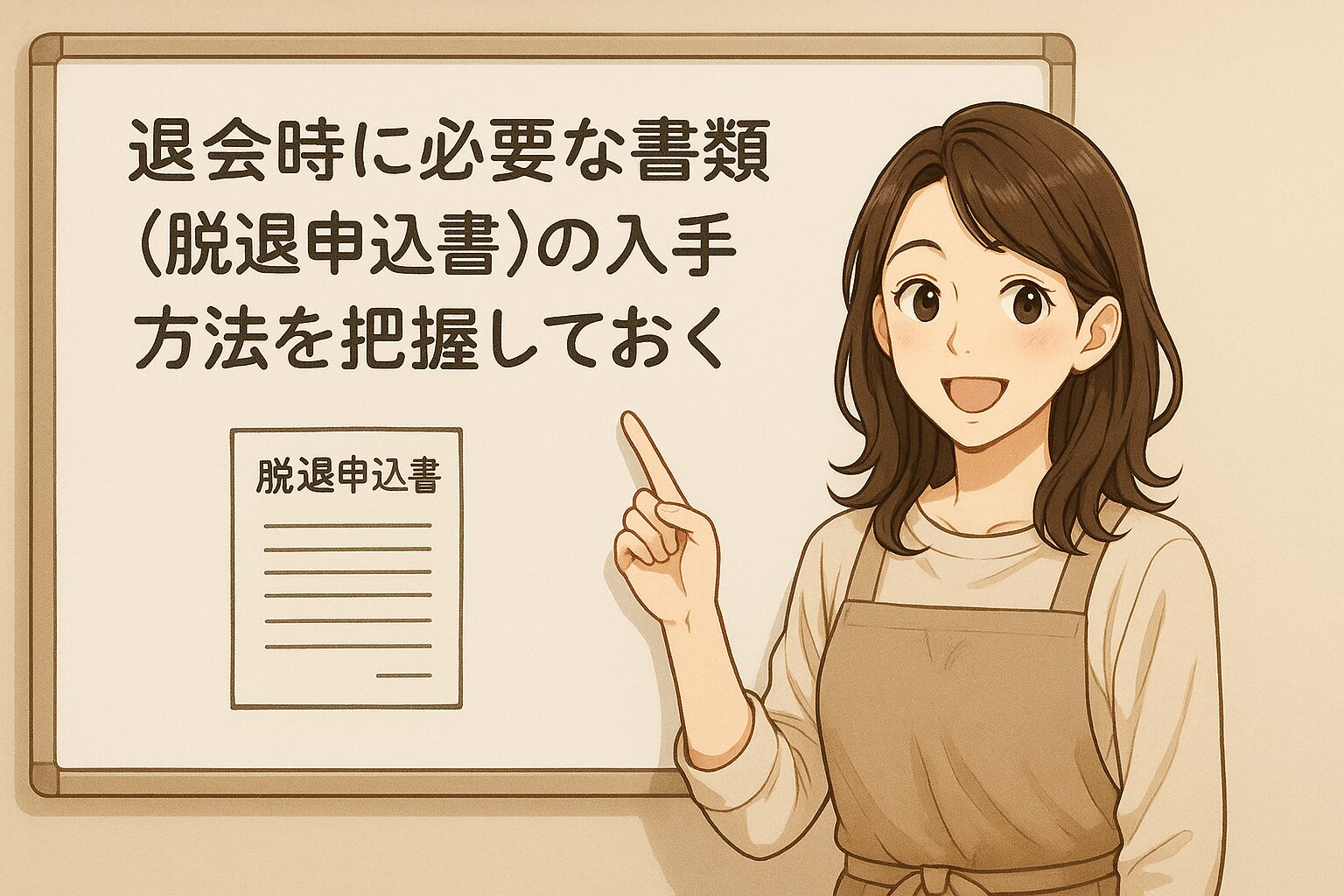
退会手続きをスムーズに進めるためには、必要書類のひとつである「脱退申込書」の入手方法を事前に確認しておくことが大切です。
脱退申込書は、コープきんきの配達担当者に声をかければ受け取ることができます。定期的に顔を合わせている方なら、次回配達時にスムーズに受け取れるでしょう。また、電話でコールセンターに連絡し、郵送で送ってもらう方法もあります。仕事や育児で時間がとりにくい場合でも、自宅に届くので手軽です。
さらに、最寄りの支所や店舗で直接受け取ることもできます。買い物のついでに立ち寄れば、スタッフからその場で申込書をもらえます。中には、買い物帰りに店舗で申請書を受け取り、そのままカウンターで書類を記入して提出したという例もあります。
また、配達を休止中でも電話連絡をすれば対応してもらえるため、しばらく利用していない方でも手続き可能です。過去には、休止中の組合員が電話一本で申込書を郵送してもらい、数日で退会できたというケースも確認されています。
脱退申込書は、退会手続きに欠かせない基本書類です。受け取り方をあらかじめ確認しておくことで、思い立ったときにすぐ動ける安心感につながります。
3.出資金返還時期(年1回など)を知ってスケジュールを立てておく
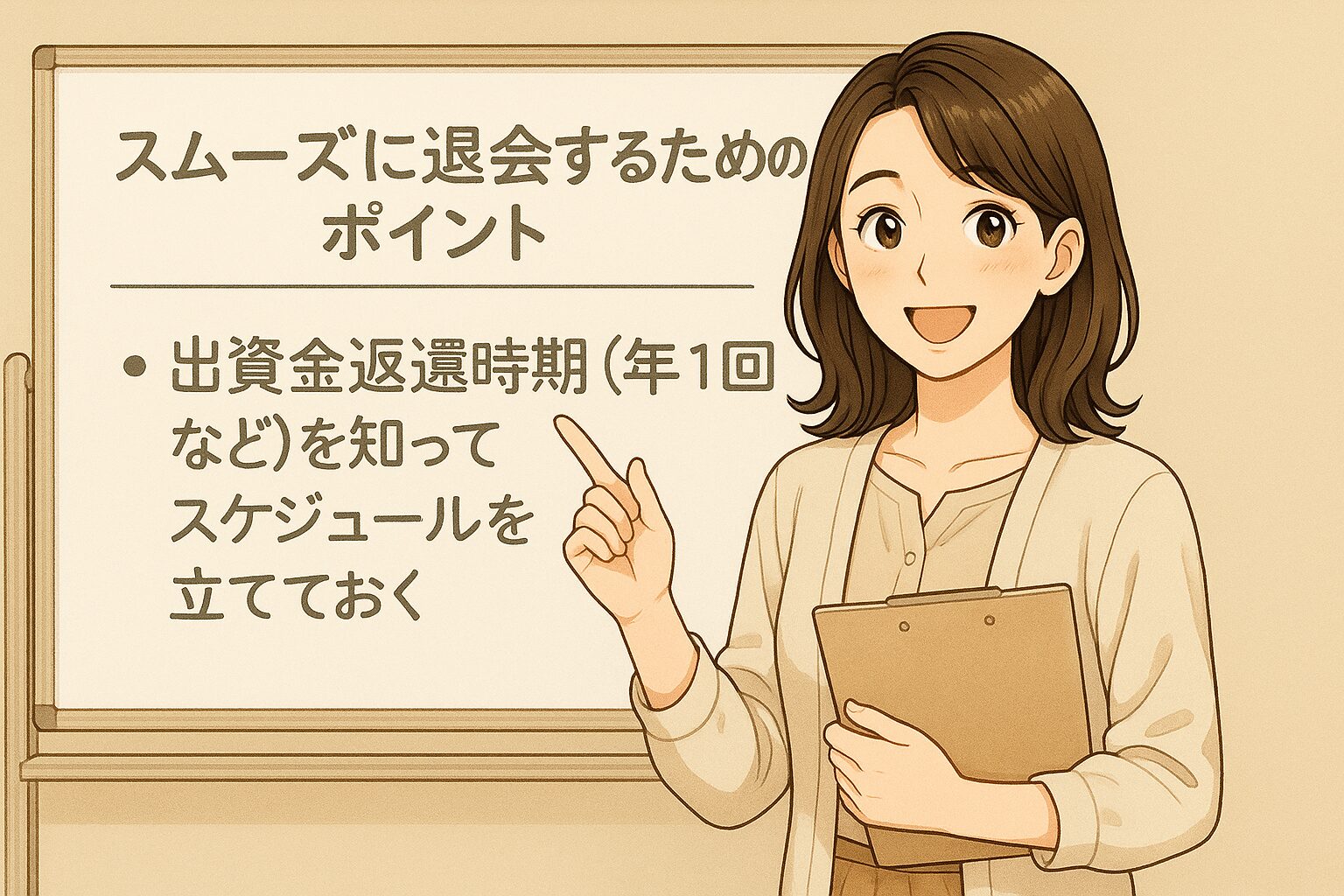
退会をスムーズに進めるカギは、出資金の返還タイミングを把握して、スケジュールを立てておくことです。
まず、退会理由によって返還時期が変わります。「法定脱退」(引越しや本人の死亡などやむを得ない事情)の場合は、申し込み後約2~3週間で指定の口座に返金されることがほとんどです。たとえば、夫の転勤で自治体間を越えて引越しした家庭では、「退会申込みから3週間ほどで出資金が振り込まれ、新生活資金にすぐ回せて助かった」との声がありました。
一方、自己都合で退会する「自由脱退」には、年度末(通常3月末)の申請が前提です。一般には事業年度末の90日前(12月末)までが目安となり、返金は翌年3~4月にまとまって行われます。たとえば、子どもの進学を機に「来年春には不要になる」と見越して、12月中に申請したご家庭では、翌年の春休みに合わせて出資金が戻り、「入学準備費に充てられてありがたかった」といった実例があります。
さらに、全額ではなく一部だけ払い戻す「減資」にも、自由脱退と同じ年末申請・翌春返還のルールがあります。たとえば、出産前に出資金の一部を減資しておき、「春に戻ってくるお金で子ども用品を買えた」と話している家庭もあります。
これらの違いをあらかじめスケジュール帳に書き込んでおくことで、「いつ申し込めば、いつ返ってくるか」が明確になり、不安なく退会手続きに臨めます。特に、年度末や引越しシーズンは処理が混雑しやすいため、余裕をもって申し込むことが大切です。
出資金は、大切な資金でありながら、戻ってくるお金でもあります。用途に合わせて申請理由と時期を正しく選ぶことで、スムーズに手続きが完了し、家計の管理もしやすくなります。
4.加入時に受け取る「組合員番号」を記録しておく

コープきんきの退会をスムーズに行うためには、加入時に受け取る「組合員番号」をしっかり記録しておくことが重要です。
組合員番号は、脱退申請書にも記入が必要な基本情報で、配達担当者や店舗窓口、電話連絡でも必要になります。見当たらない場合、問い合わせに時間がかかり、手続きが遅れる原因にもなります。
たとえば、引越しに伴う法定脱退の際に、「組合員番号を事前にメモしていた家族」は、申請書を受け取ってから直ちに記入・返送ができ、約2週間で出資金が返金されるスムーズな流れで安心だったそうです。
また、育休が終わって再加入を検討した家庭では、以前の番号を控えていたため、簡単に再加入の手続きができ、新しい組合員証やアプリログインもスムーズでした。過去の会員情報引継ぎに苦労しないのもメリットです。
さらに、配達を一時休止した後で再開する際も、組合員番号を伝えるだけで元の配達曜日・時間帯を優先的に設定してもらえたといいます。「番号さえあれば、電話一本で以前の状態に戻せて便利だった」という実体験もあります。
逆に控えておかずに申請書に空欄があると、配達担当者が番号を調べに支所に連絡する必要があり、「ただいま確認中です」と数日待つケースがあります。特に年度末や引越しシーズンはサポート窓口も混雑しやすく、思い通りに手続きが進まないことがあります。
加入時に届く書類の中に組合員番号が記載されていますので、メモ帳やスマホのメモ、または専用フォルダーにまとめて保存しておきましょう。さらに番号をスクリーンショットしておけば、ネット注文eフレンズへのログイン時にも役立ちます。
番号をあらかじめ控えておくことで、退会・再加入・休止・再開などの手続きがすべてスムーズに進み、ストレスなく次のステップへ移れるという安心も得られます。
5.注文最終日の確認と、退会時点の注文状況を把握しておく
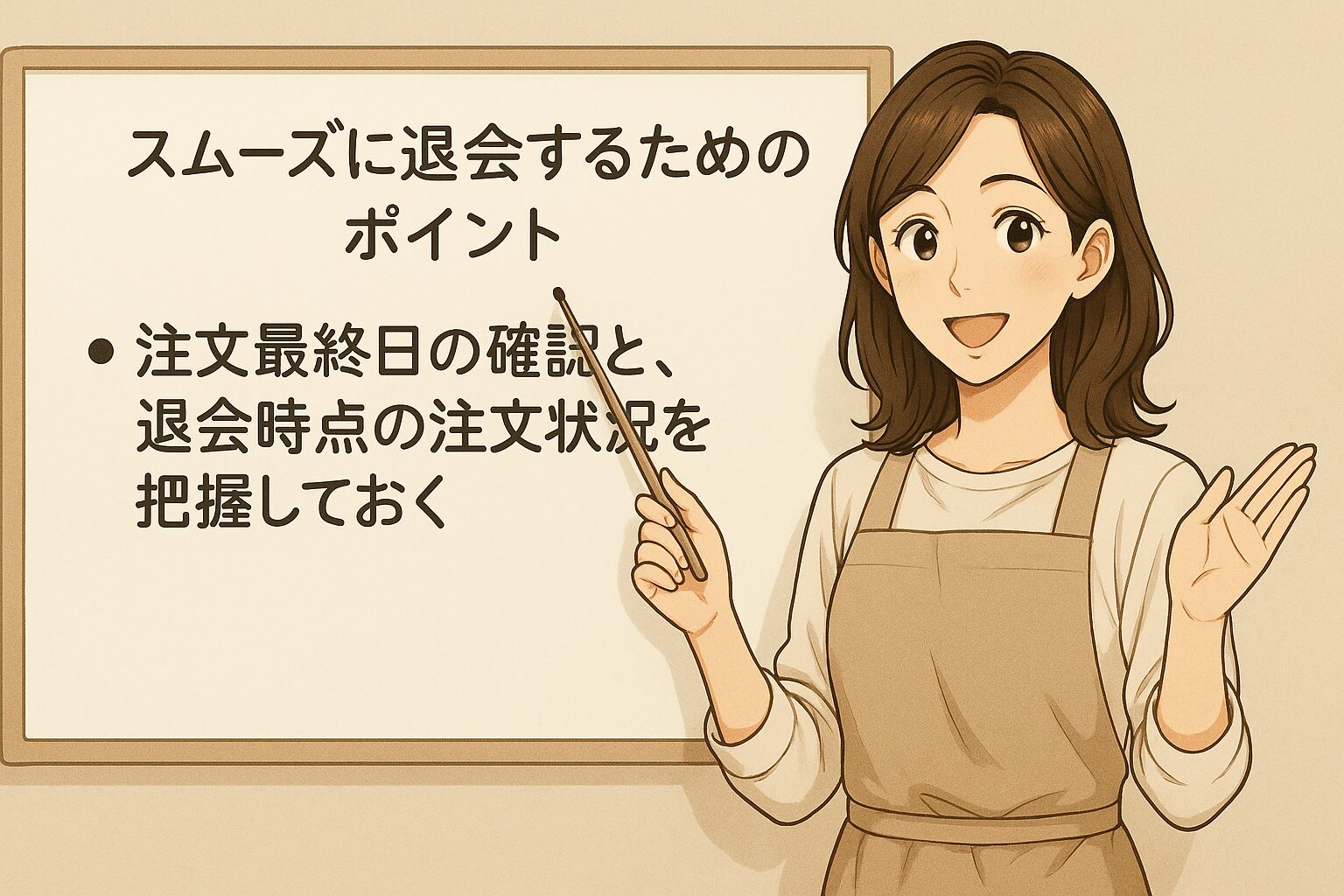
退会をスムーズにするためには、「注文最終日」を確認し、退会時点でどんな注文が残っているかを把握しておくことが大切です。
まず、脱退申込書を提出する前に、eフレンズや紙の注文カタログで「最終配送週」とその締切日を確認します。配送スケジュールは季節によってずれやすく、うっかり直前の注文を逃すと、退会希望日以降に商品が届いてしまう可能性があるため注意が必要です。
たとえば、ある家庭では「3月15日締切、3月22日配送が最終週」であることを把握していたため、3月14日に注文をすべてキャンセルし、申込書を提出。翌週から配達が止まり、注文漏れもありませんでした。
また、別のケースでは「冷凍庫に残っている食品がある状態で最終配送を迎えた」ご家庭が、納品リストを確認しながら必要なものだけ注文し、それ以外は注文を見送ることで、在庫過多や無駄買いを防ぐことができました。
さらに、配達休止や退会を一緒に進めたママ友の例では、最終日の注文が仮注文のままになっていたため、支払いや配送のトラブルになりかけました。事前にログを印刷して担当者に相談し、未確定分も含めて処理してもらい、無事に退会できたと言います。
こうした状況を避けるため、退会を考えた時点で「最終注文日」と「締切日時」をカレンダーに書き込み、注文内容も一覧化しておくのが有効です。eフレンズの「注文履歴」やアプリの「カート」もチェックし、確定済み・仮確定の両方について確認します。
退会当日までの不要なストレスを防ぐポイントはこれだけです。注文最終日をしっかり把握し、キャンセルや必要品の確認を計画的に行えば、退会後の配送ミスや請求ミスを未然に回避できます。
6.退会後に失効するポイントや特典の扱いを理解しておく
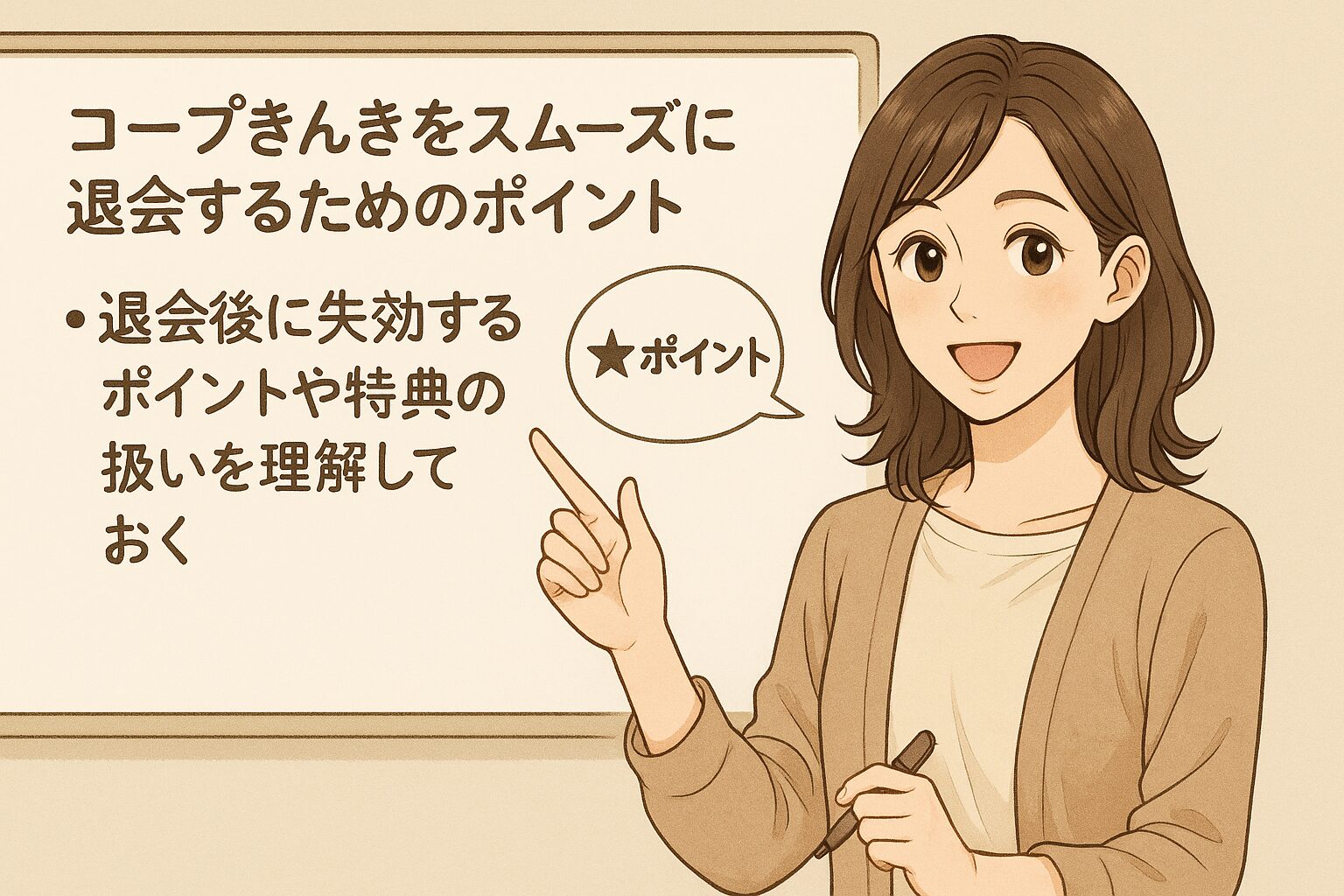
退会後に「貯めたポイントや特典がどうなるか」を理解しておくことは、安心して退会を進めるうえで重要なポイントです。
まず、コープには「コーピーポイント」やeフレンズ限定の投稿ポイントなどがあり、それらは退会と同時に失効することが多いです。たとえば、コープこうべでは、ポイントは進呈年度の翌年度末(3月31日)までしか使えず、退会時には未使用分が戻ってきません。
具体的なケースとして、育休期間中にeフレンズのレビュー投稿で100ポイント貯めた方が、退会直前に気づいて急いで使い切った例があります。退会後に使えないと気づいて後悔されたそうです。
また、「お友達紹介」や「キャンペーン特典」として付与されたポイントも対象です。たとえば、クチコミ投稿キャンペーンで最大200ポイントが付与されたものの、退会タイミングが遅れて約50ポイント分が期限切れとなり、もったいなかったという声もあります 。
さらに、紙面や店舗で使えるクーポンなどの特典も同時に消失します。例えば、組合員向けの店舗割引クーポンを配布されたまま退会し、使わずに終わったという方もいました。こうした損失は、生活費に響くこともあるため、事前に使い切る計画が必要です。
失効を防ぐための対策としては、
- 退会前に保有ポイントを把握し、一括使用する
- eフレンズでの投稿ポイントもチェックし、レビュー投稿を行いポイント獲得後すぐ利用
- クーポン類も注文時に確実に適用する
といった方法が効果的です。
生活費の助けになるポイントを無駄にしないために、「退会時には使い切る」という前提でスケジュールを組んでおくことが安心につながります。一度計画的に使い切ってから手続きを進めれば、家計にも心にも余裕を持ってコープ卒業ができます。
7.「一時休止」と「退会」の違いを理解しておく
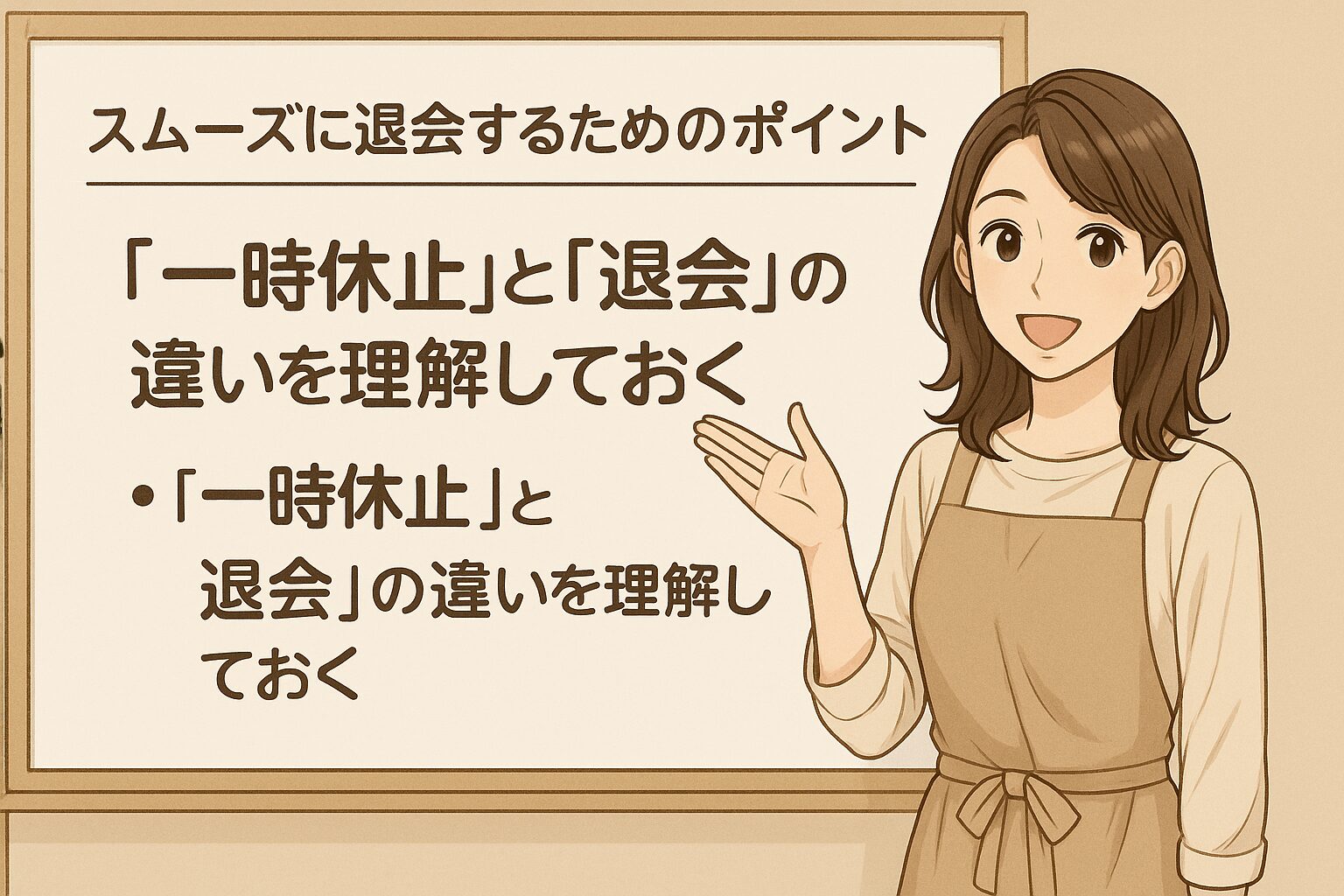
「一時休止」と「退会」は似ているようで異なる制度です。それぞれのメリットを理解し、目的に応じて活用することが、スムーズな手続きにつながります。
まず「一時休止」は、配達のみを停止する制度で、最大6か月まで利用できます。休止中は配達手数料や積立出資金は発生せず、ポイントや共済契約もそのままキープされます。たとえば、里帰り出産や長期の帰省、真夏・真冬の旅行など、数週間〜数か月の一時的な予定がある家庭では「休止」を使って安心して家計管理ができました。
一方「退会」は組合員を完全にやめる制度です。配達はもちろん停止され、脱退申込書の提出後には出資金が返金されますが、保有ポイントや共済契約は失効してしまい、再加入には再度出資が必要です。たとえば、転居して配送エリア外になるご家庭では退会が必要ですが、再加入の手間を考えるなら、引越し前後で休止をうまく併用する人もいます。
具体例として、
- 里帰り出産で3か月家を空けるママは、一時休止を選び、戻った週に電話で再開連絡のみで済みました。
- 夫の単身赴任で半年間配達が不要になった家庭は、休止中に手数料がかからず、復帰もスムーズでポイントも減らず助かったとの声があります。
- 小学校入学後、生活リズムが変わり注文が減ってきた家庭は、退会を選び出資金を返金。無駄な積立を防ぎつつ生活圏が変わるタイミングで区切りがつきました。
理解しておくべきポイントは、
- 一時休止は配達のみストップ、出資金・ポイント維持
- 退会はポイント消失・共済解約・出資金返金で完全区切り
です。利用予定が再びあるかどうか、保障やポイントを残したいなら休止、配送エリアが変わる・利用予定がないなら退会、と目的に応じて選ぶことで、余計な手間や損を回避できます。事前に制度の違いを知り、手続きを賢く選ぶことが共働き主婦にはとても役立ちます。
8.脱退の意志表示は早めにしておくと手続きが混雑せずスムーズ
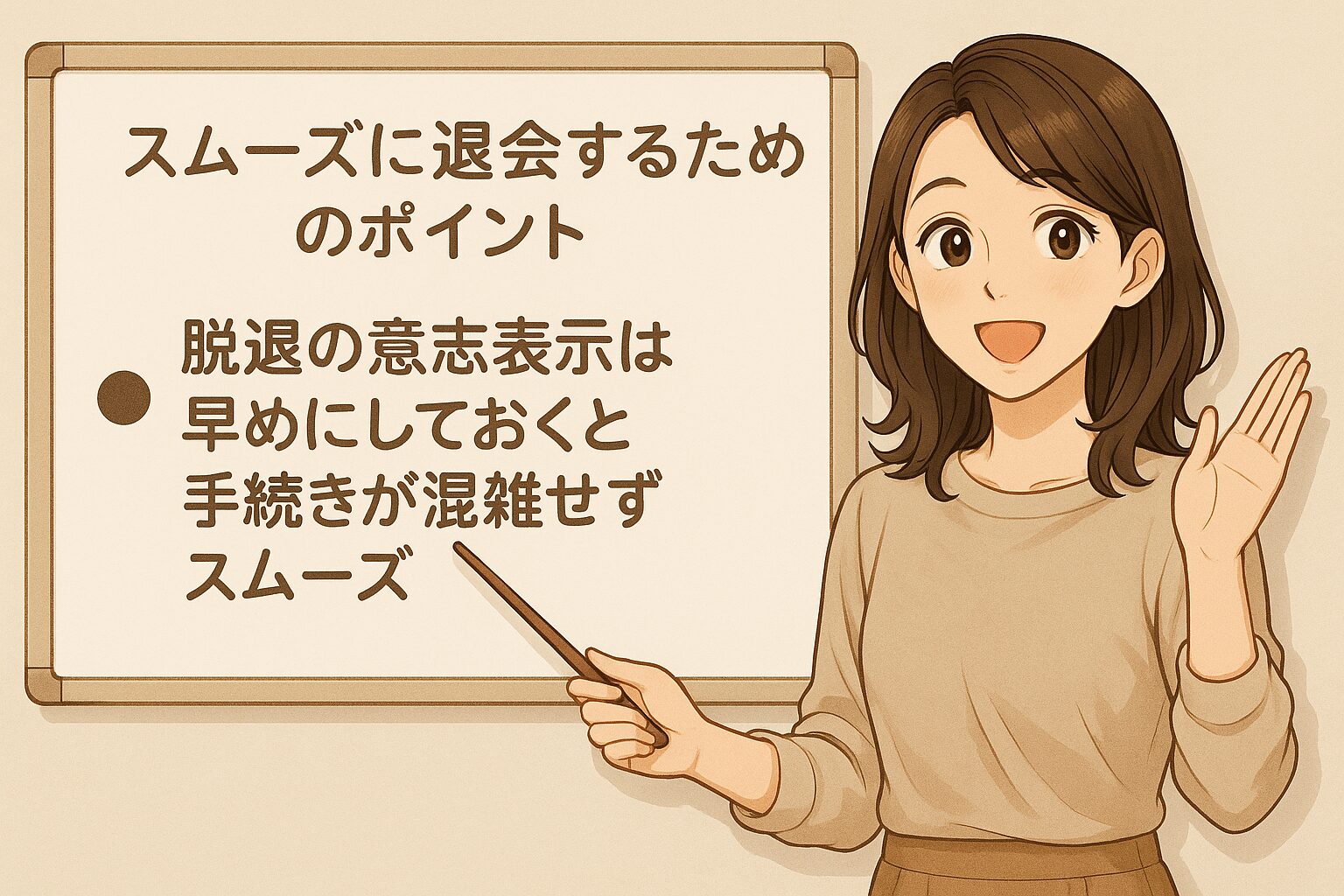
脱退の意志表示は早めにしておくことで、事務手続きが混雑せずスムーズに進みます。特に年度末や引越しシーズンは手続きが集中し、対応に時間を要することも少なくありません 。
たとえば、3月に引越しして退会を希望した家庭が、2月中旬に電話連絡して申込書を郵送依頼したところ、混雑前に書類が届き、申し込みからわずか10日以内に出資金返金を受け取れた例があります。
別のご家庭では、転勤が決まったときに早めに配達担当者に一言伝え、2月上旬に書類を準備。混雑前のタイミングで申請が通り、手続き完了までストレスなく進められたとのことです。
また、育休明けに退会を考えたママ友は、あらかじめ申し込み時期をカレンダーに入れ、余裕をもって2月末に申請。「3月に入ってからでは窓口が混雑しやすい」と当日の提出を避け、30代ワーママにとって時間的にも精神的にもゆとりある退会ができました。
混雑時期に申請すると、脱退申込書の処理に数日~数週間かかることがあり、eフレンズの回答遅れや電話がつながりにくくなることもあります。
混雑を避けるポイントとして、
- 年度末の2か月前(1~2月)に意志表示
- 配達時に配達担当へ口頭で伝える
- 電話または支所窓口で書類を取り寄せ、記入後即提出
といった手順を取ることで、待ち時間を抑えながらスムーズな退会が可能になります。
脱退書類の提出から出資金返金までは、法定脱退でも自由脱退でも混雑時期を避ければ最短2〜3週間。先に申請すれば、春休みや新生活準備などに合わせて家計資金を先取りでき、安心して次のステップに進めます。
9.再加入する場合の条件や制限について調べておく
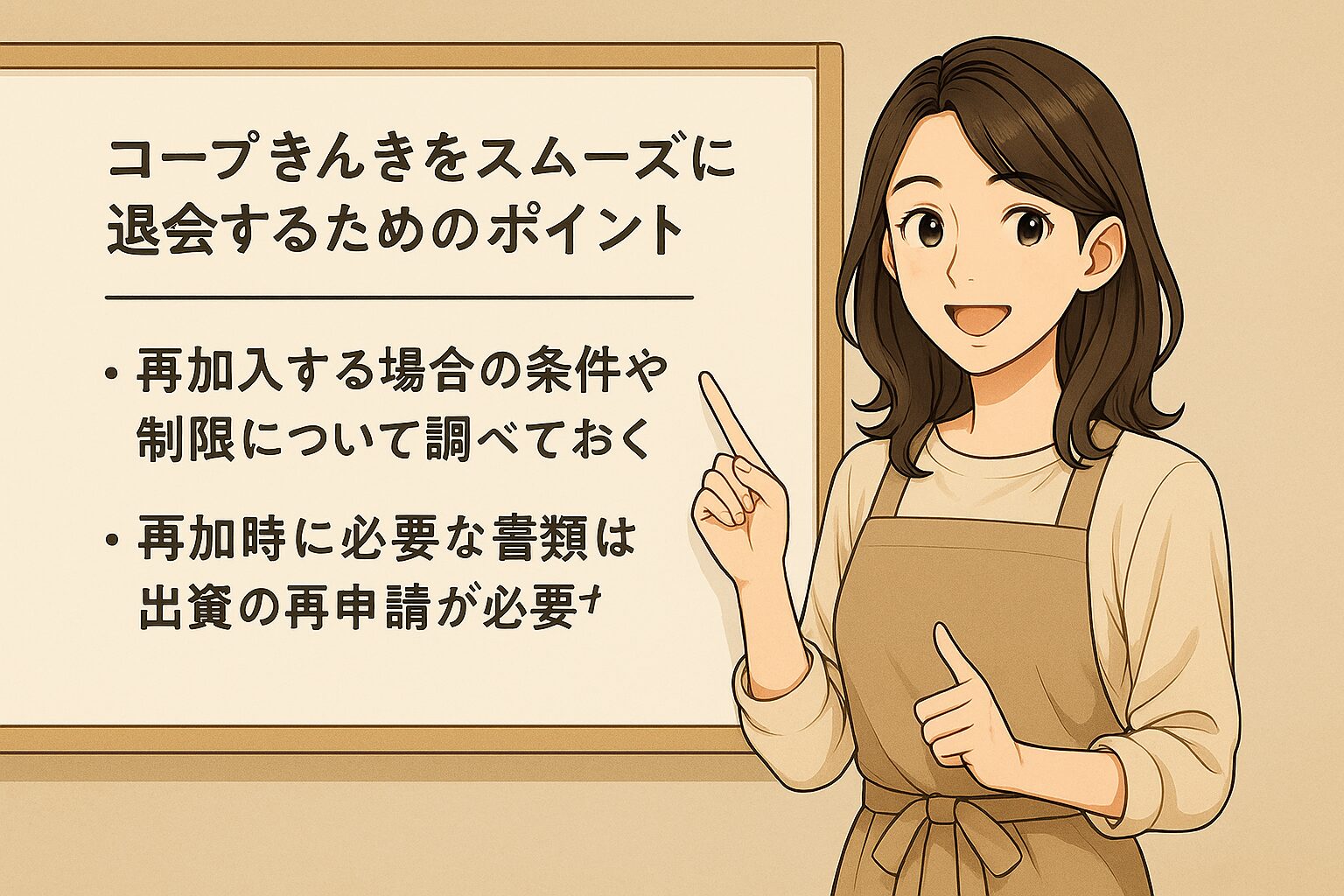
コープきんきを再利用したいとき、再加入の条件や制限を事前に押さえておくことで安心して手続きできます。
まず、以前に脱退した組合員でも、再度加入することは可能です。ただし、再加入は「新規加入」として扱われ、改めて出資金の預託や加入手続きを行う必要があります。
例えば、夫の転勤で脱退した後、2年半経って近隣へ戻ってきたご家庭では、再加入手続きがスムーズに進み、再び宅配を利用できたというケースがあります。新規扱いのため加入特典や初回割引も受けられる場合があります。
また、育児がひと段落した際に自由脱退したママ友は、半年後に「やっぱり便利」と感じたため再加入。こちらも通常の加入手続きと出資金が必要でしたが、以前の番号やポイントは引き継げず、再度0からスタートしました。
一方、キャンペーンのために退会→短期間で再加入した家庭は、再加入キャンペーンの対象外だった例があります。再加入でも新規加入扱いですが、生協によっては「過去利用歴がある組合員への特典制限」があることもあるため、事前に確認が必要です。
そのため、再加入を考えたときには、
- 脱退してからどのくらい期間を空ければ特典を受けられるか
- 出資金の再預託額(通常500〜1000円程度)がいくらか
- 過去の組合員歴が再加入特典にどう影響するか
といった点を、公式サイトやコールセンターで確認しましょう。
再加入には資格や利用条件の変更がないかもチェックが必要です。例えば、引越し後に加入エリアが変わる場合、別の生協への加入手続きが求められることもあります。
以上を踏まえ、「いつ」「どんな特典で」「いくら必要か」を把握しておくと、再加入の判断とスケジュールに余裕が生まれ、家計や時間の無駄を防げます。
10.「組合員証」や「出資証書」は手元に保管しておくと退会時に安心
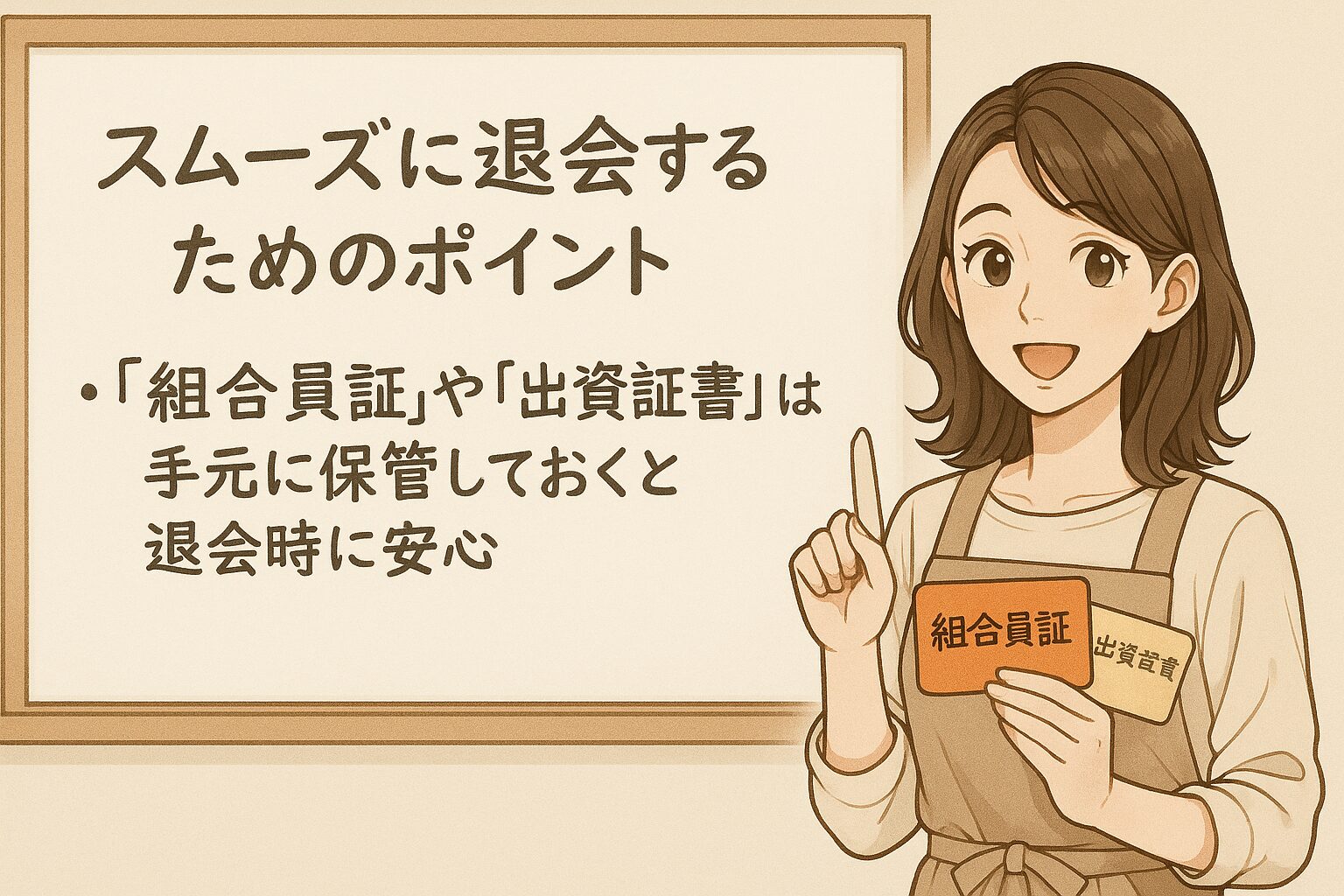
組合員証と出資証書を手元に保管しておくと、退会時の書類記入や出資金返金が格段にスムーズになります。どちらも加入時に郵送または配達担当者から受け取る紙またはカード形式の証明書で、組合員番号や出資額が明記されています。脱退申込書にはこの番号や出資額を正確に転記する欄があり、紛失していると問い合わせや再発行に手間がかかります。
たとえば、引越し準備で多忙な中でも組合員証をすぐ提示できたご家庭は、配達員がその場で脱退申込書を記入代行し、わずか一週間で出資金返金の手続きが完了しました。
一方、証書を紛失していた別の家庭は、支所に再発行を依頼することになり、証明書再発行と本人確認で二週間、さらに返金処理に二週間と、退会完了が当初予定より大幅に遅延したそうです。
また、在宅ワークのママがスマホで証書の写真を保存しておいたケースでは、原本を探す時間がいらず、オンライン問い合わせに画像添付で即座に本人確認が取れたため、窓口へ行かずに脱退申請が完了しました。
ポイントは、加入後すぐに「①紙の証書をクリアファイルへ」「②スマホで両面を撮影」「③番号を家計簿アプリのメモ欄にも控える」の三段構えでバックアップしておくことです。これだけで紛失や再発行のリスクを減らし、退会時の問い合わせ時間や書類待ち時間を短縮できます。
家計と時間の両面でムダをなくすために、組合員証と出資証書は大切に保管し、デジタルでも控えておくことをおすすめします。
まとめ
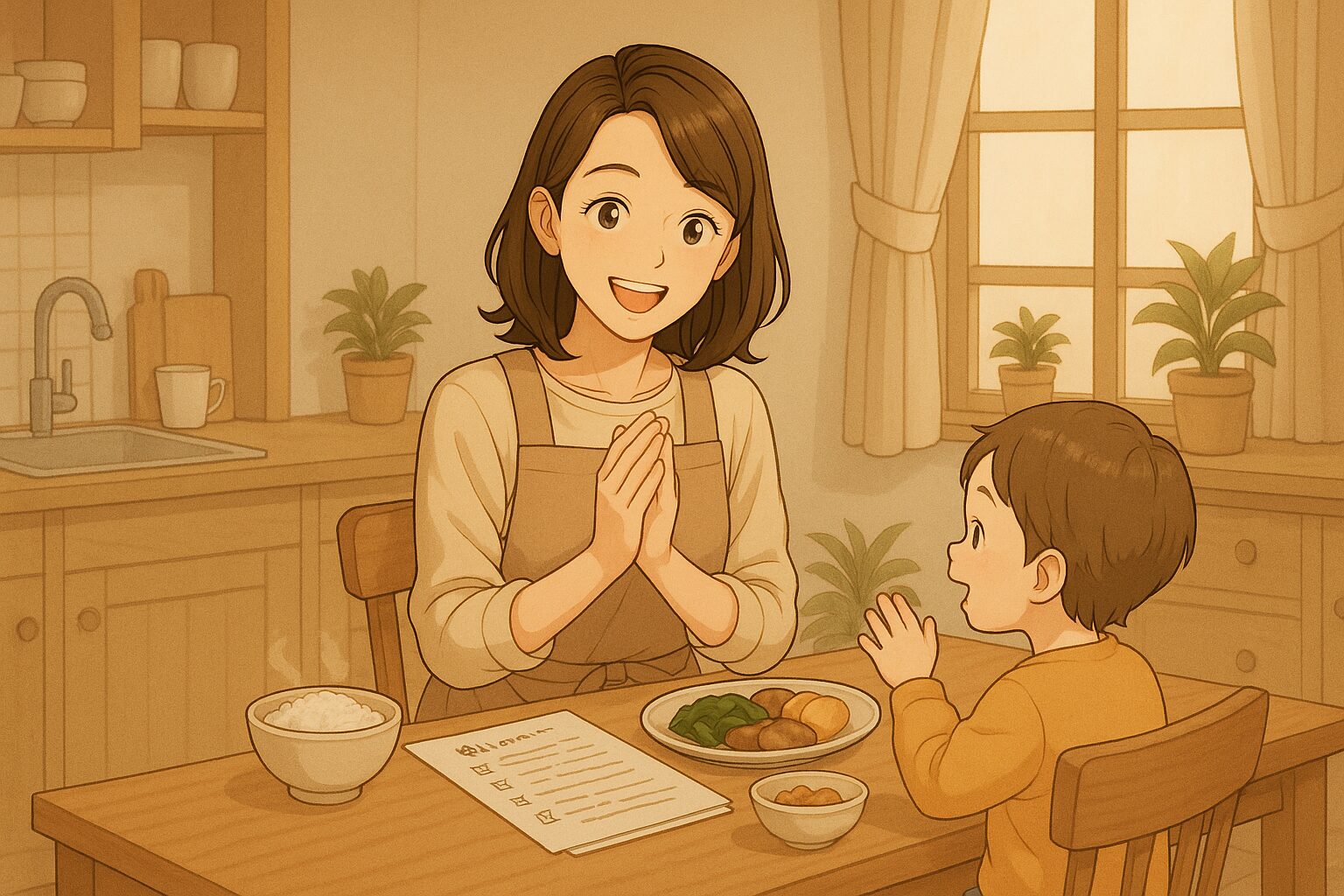
コープきんきの退会を検討する際、多くの方が「手続きが煩雑ではないか」と不安を抱きがちです。しかし実際には、脱退の意思表示を早めに行い、必要な書類や情報を前もって準備しておけば、スムーズに進められる手続きです。本記事では、退会時の具体的な準備として、申込書の入手方法や提出タイミング、注文最終日の確認方法などを丁寧に解説しました。
また、退会後に失効してしまうポイントや特典についても、退会前に使い切ることで無駄なく活用できるようになります。加えて、一時休止と完全な退会の違いを把握しておくと、将来再び利用する可能性がある場合にも安心です。さらに、再加入の際にかかる出資金や手数料、利用条件についても確認しておくと、今後の選択肢が広がります。
この記事の内容をふまえて、退会時に感じる不安が少しでも和らぎ、日常の中で納得のいく選択ができる手助けになればと願っています。退会は終わりではなく、次の暮らしのスタイルへ向けた一歩として考えていくことができます。
(※ご注意!ここで紹介しているデータは、2025年6月21日時点での独自による調査結果です。各データは、必ず運営会社発表のものと照合しご確認ください)










